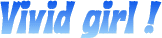「え? 相模? あれ? 斎は……」
「大事な用事があるとかで、さっき帰った。大丈夫か? えらく泣いてたな」
泣いているところを好きな男に見られるのは、かなり恥ずかしいことだ。絢子は顔を真っ赤にして、布団に埋まった。熱のせいで元々顔は赤いのだが、本人には分からない。
相模は、ちょっと困ったような表情を浮かべて、ベッド脇に膝を付いた。もう一度絢子の額を触ると、やはりまだ相当熱い。
幼馴染の氷室が傍にいた方が、彼女にはずっといいだろうに。赤の他人である自分がいても、出来ることは少ないし、彼女も心細いはずだ。そう言って引き留めたが、氷室は妙に自信たっぷりに「お前がいた方が、断然いいって」と言って、さっさと帰って行ってしまったのだ。
とりあえず出来上がった雑炊を前にして、どうしたもんかと考える。いくら何でも自分まで帰ってしまったら、彼女があまりにも気の毒だ。そこで、とりあえず出してあった器に雑炊を移し、トレイに乗せてダイニングテーブルに置いてきたのだ。器やレンゲを用意までしておいて帰ってしまうとは、幼馴染のくせに薄情な奴だ。
そんな氷室を思い出して溜め息をつくと、相模は布団の中の絢子を覗き込んで訊いた。
「結城、雑炊作ったんだが、食べられるか?」
「……食べる」
ひょこっと布団から顔を出して、彼女がボソッと言う。
「起き上がれるか?」
「ん……」
絢子は布団を捲って体を起こそうとしたが、力が入らないのかウンウン唸っているだけで、中々上体を起こすことが出来ないでいた。
相模が背中に腕を回してやると、突然の介助に素っ頓狂な声を上げる。
「うひゃっ」
「あ、悪い。どこか痛かったか?」
「う、ううん、そうじゃなくて。ちょっとビックリして……はりゃ?」
彼のお陰で起き上がれたのはいいが、支える手がないと体が簡単に倒れてしまう。熱に浮かされているために体の自由が利かず、絢子はもどかしくて仕方がなかった。布団に仰向けになっている彼女を見下ろして、相模はしばし考えた。
ふと、視線を向けたところに、丁寧にたたんである服があった。立ち上がって見に行くと、オレンジ色のスウェットの上下だ。中にタオルが挟んである。おそらく、氷室が出して行ったのだろう。それを持ってベッドに近付く。
「これ、結城の服か?」
「え? あ、うん、それあたしの……なんで相模が?」
「そこに出てた。今背中触ったら、汗でビッショリ濡れてたからな。とりあえず着替えた方がいいだろ」
「うん。でも、雑炊は?」
熱で赤い顔をしていながら、それでも食欲のある様子に、相模はおかしそうに少し笑った。
「な、なによぉ」
「いや、悪い。病気になっても、食欲があるのはいいことだもんな」
「むっ……バカにしてる?」
「してない。安心したよ」
「え?」
「食欲があるなら、回復に向かってる証拠だろ。だから安心した」
絢子には思い掛けない彼のセリフと笑顔で、呆けた顔を露呈してしまった。そして、相模の手がくしゃくしゃと頭を撫でるに至って、絢子は恥ずかしそうに顔を赤らめて布団を引っ張った。
「結城、靴下はすぐに出せるか?」
「え、え? 靴下?」
「食事するなら、ちゃんとテーブルに着いて食べた方がいいだろ。体を冷やしちゃマズイからな。どこにある?」
「あ、それなら。そっちのタンスの真ん中にある、小さい引き出しに」
絢子の説明を受けて、相模が立ち上がって行く。
熱のせいだけではない激しい動悸を抑えながら、絢子は相模の手が触れたところを、しきりに自分で撫で回した。中等部からバスケ部で一緒にいるが、こんなに彼に触ってもらったことは、今まで一度としてなかったのだ。先月保健室に連れて行かれた時の抱っこでさえ、あれが初めてのことだった。
嬉しいと感じると同時に、つらくもなる。これからずっと、こんな気持ちを抱えていかなくてはいけないのだろうか・・・。
「これでいいか?」
相模が持って来たのは、少し厚めの見るからに温かそうなのだった。
「うん、ありがと」
「じゃ、俺は向こうで待ってるから、着替え終えたら声を掛けろよ。タオルも一緒に入ってるから、体を拭くんだぜ」
「ん」
パタンとドアが閉まるのを待って、絢子は仰向けに寝たまま深い溜め息をついた。
「ダメだなぁ。やっぱり、相模のこと好きだよ。でも、今の相模に告白したって、迷惑なだけだよね……」
改めて言葉にすると、涙が込み上げてくる。
「こんなことなら、もっと早く……好きになった時に言っちゃえばよかった。やっと、告白する気になれたのに……。つらいよ、こんなの……もう消えちゃいたいよ。こんな気持ちのままで、ずっと、いたくない……どうすればいいの?」
目尻からポロッと涙が零れ、絢子は慌ててそれを拭い、寝たままの状態でパジャマのボタンを外し始めた。
**********
一方の相模は、猫舌の彼女のために雑炊を冷ましているところだった。器に盛ってから多少時間が経っているので、出来立てよりはマシだったが、やはりまだ熱かったのだ。
程好く冷めて満足したところで、壁に掛かった時計を見る。部屋を出てから5分経った。そろそろ着替え終わった頃だろう。
彼はダイニングテーブルから離れ、絢子の部屋のドアをノックした。
「結城、着替えたか?」
「あ、うん。終わったよ」
部屋に入ると、彼女はちょうど靴下を履いているところだった。一つ一つの動作がゆっくりで息も苦しそうではあるが、一人で動けるということはかなり回復してきたのだろう。
「上に着るもの、何かあるか?」
「え? ううん、この時季だから何も出してないけど……」
質問の意味が分からず、絢子は首を傾げた。ふむ…と考えて、相模は続ける。
「寒気は?」
「ちょっとだけ」
「まぁ、食事すれば温まるか」
「へ? わっ」
屈んだ彼の腕が、ベッドに座っている自分の背中と足を抱えたので、絢子は驚いた。
「ちょっ、相模!?」
「歩くのはまだつらいだろ?」
「それは、そうだけどっ」
皆まで言わない内に、絢子は相模に抱き上げられてしまった。しかも彼の右腕が背中を抱えている。ということは、自分の左側が相模に密着しているわけで。
『心臓がドキドキしてるの分かっちゃったら、嫌だな。相模が好きだって気付かれでもしたら、迷惑だろうし……』
それに、着ているスウェットの下は素肌なのだ。この前のようにTシャツの下にブラをしていれば別だが、今は違う。何だかとてつもなく恥ずかしくなってしまった。
ふと、制服姿の相模から、柑橘系のいい香りが漂っているのに気付いた。が、何か言うと心臓が口から飛び出しそうなので、黙ったまま絢子はダイニングルームまで、大人しく抱かれて移動した。