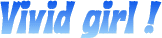ダイニングテーブルの椅子に降ろされた絢子は、目の前にある雑炊の美味しそうな香りを嗅いだ。
「相模って料理出来るんだ。凄いね」
「大した物じゃないだろ。一人で暮らしてる結城の方が、よっぽどいいもの作れるんじゃないか?」
「でも自分で食べるだけだから、あんまり手の込んだものは作らないし。斎なんか、お湯を沸かすのも苦労してるよ」
笑いながら言った時、パサッと肩に何か掛けられ、絢子は怪訝な顔でそれを見た。それはバスケ部で使っている、相模のジャージだった。自分を連れて来てから、リビングに置いてある鞄を物色していたと思ったら、これを出していたのだ。
「え? これ……」
「無いよりはマシだろ。最近は殆ど使ってないから、汚れてないし。体冷やすとマズイからな」
彼の優しい気遣いに、じ〜んっと心が和む。しかも、好きな人の服である。
「袖、通してもいい? その方が、あの…寒くないし」
「別に構わないぜ。でも大き過ぎるだろ」
それがいいんじゃないの! 絢子は心の中で突っ込む。相模はキッチンに立って、お茶を淹れているようだ。その後ろ姿にポーッと見惚れてから、いそいそ腕を通してみた。袖口までたっぷりと余っている。絢子は嬉しくなって、そのジャージの懐をクンクン嗅いだ。さっき抱き上げられた時に、彼の体から漂っていたコロンが微かに香る。
はぁ〜幸せ……と思って顔を上げたら、呆気に取られた相模と目が合ってしまった。
絢子は気まずい思いで下を向いた。
コトンッ。
カップが置かれる音にハッと顔を上げると、向かいの席に相模が座っていた。自分と彼の前には湯気の立つマグカップ。
「早く食べないと、冷めるぞ」
何事もなかったかのような言葉と態度に、ホッとしつつも絢子は心中で冷や汗をかいていた。
変態と思われたらどうしよう!? と、要らぬ心配をしていたのだが、相模の方は熱で行動がおかしくなっていると思っているので、本当に要らぬ心配であった。
そんなことは露知らず、絢子は慌ててレンゲを手に取った。
「あ……う、うん。いただきます」
レンゲで汁とご飯をすくいながら、絢子は目の前に座る彼をチラッと盗み見た。
ドキンッ!
相模の視線が自分に注がれていて、心の中で「ひゃ〜っ」と慌てた。妙に優しげな眼差しは、何か意味があるのだろうか? 彼も自分を好きでいてくれたら、それだけでも嬉しいのになぁ、と詮無いこと考えながら、すくった雑炊を口に入れた。
「……!」
瞬間、固まってしまった絢子。相模が怪訝そうに見る中、今一度雑炊を食べる。そして、再び固まった。
雑炊を二口啜ったまま凝固してしまった絢子を、相模は眉をひそめながら、身を乗り出して覗き込んだ。
「結城? どうしたんだ?」
「お…美味しい」
どこか呆然とした顔でポツリと言う。相模は、ふっと破顔した。
「それはよかった。結城の口に合って」
しかし、絢子は難しい顔をして黙り込んでいる。彼の笑顔を眼前に見たというのに、反応がない。
「結城?」
「へ? あ、うん。美味しいよ、凄く」
信じらんないくらい美味しい。
「ね、ねぇ、これウチの台所で作ったんだよね?」
「あぁ」
「ウチにある材料で作ったんだよね?」
「? ああ。何かマズかったか?」
「そうじゃなくて……。同じ台所で同じ材料使ってて、こんなに違うんだなぁって…」
女であるが故に、好きな男の方が料理が上手いというのは、かなり複雑な気分だ。だが、相模にはそんな乙女心は分からない。
「そんなに特別美味いってことはないと思うぞ。それより、早く食べて寝た方がいいんじゃないか?」
「……うん」
まだ釈然としがたい表情をしていたが、絢子は手と口を動かすことに専念した。
相模が冷ました雑炊は、彼女にとって食べごろだったようで、あっという間に完食した。
「ごちそうさま。美味しかったよ」
相模がこんなに料理が上手いなんて、ちょっとショックだったけど・・・。
目の前から相模が立ち上がる気配がして顔を上げると、コップにミネラルウォーターを注いでくれていた。それと一緒に差し出されたのは、消炎鎮痛剤。絢子はそれをしげしげと見つめた。
「え? 痛み止めでいいの? 風邪薬じゃなくて」
「咳とか鼻水が出てる訳じゃないだろ。風邪じゃないからな。熱冷ましだけで十分だろ。熱が下がれば、もっと体が楽になるぜ」
絢子は頷いて彼から薬を受け取り、水で流し込んだ。
「部屋に戻るか?」
「その前に歯磨きとトイレに行きたい」
「ん、そうだな」
そう言って立ち上がった彼が、また自分を抱き上げようとしたので、さすがに慌てて立ち上がった。
「も、もう一人で歩けるから平気だって!」
「うん? そうか。つらくなったら言えよ。すぐ行くから。俺はコレ片付けておく」
自分が食べた食器を持った相模を見て、絢子は順番を間違えたことに気が付いた。
「ご、ごめん! それ私が片付ける」
器を取ろうとした彼女の手から、相模は身長に物を言わせてそれを高く上げてしまった。
「相模」
「病人は大人しく寝てろよ。早くしないと、体を冷やしてまた熱が上がるぞ」
「でも……」
「気にするなって。勝手に台所使ったのは悪かったけど、もう今更だろ。そんなことより、早く治すことを考えろよ。結城がいないと、みんながだらけて困る」
彼女の頭をポンポンと撫でて、相模はキッチンに入って行った。絢子は撫でられた頭を押さえながら、しばしその後ろ姿をボーっと眺め、顔を真っ赤にして洗面所に飛び込んだ。
「うわーん、どうしよぉう! これって絶対……こ、こ、恋煩いのせいで熱が出るなんて、私のキャラじゃないよぉ!!」
真っ赤に染まった頬を両手で押さえた自分の姿が鏡に映る。それを見た絢子は、本気で頭を抱えてうずくまった。
「こんなの……どうしたら治るって言うのよ。絶対治る訳ないじゃん。やっぱり言った方がいいの? ……でも、言ったら、告白したら、きっと相模に迷惑が掛かるもん。どうしたらいいの?」
悶々と悩む彼女の脳裏に、ふと、母親のことが思い浮かんだ。
母親の最期を看取ることが出来なかった自分。病院に着いて、息をしていない母親と会った時の虚無感は、今でも絢子を苛さいなむことがある。
もうあんな後悔はしたくない・・・。
一つの決心をした絢子は、立ち上がって鏡を見た。
「そうだよね、もう、あんな思いはしたくないもん……」
もう一人の自分に向かってコクッと頷き、歯ブラシを手に取った。