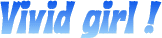「……こ、絢子」
聞き慣れた幼馴染の声に促され、絢子はうっすらと目を開けた。
天井からの電灯が、やけに眩しい。何度かまばたきすると次第に焦点が合ってきて、氷室が自分を覗き込んでいるのが分かった。
ベッドのマットが微妙な角度で沈み込んでいる。彼が絢子の寝ているベッドに腰掛けているのだ。
「あれ? 斎? 何でここにいるの?」
周囲を見回すと自分の部屋だ。彼を招き入れた記憶はない。
氷室は軽くため息をついた。
「お前、今何時か分かってるか?」
「え? 朝じゃないの?」
彼は制服を着ている。絢子の記憶では、今日初めて目を覚ましたのだが。
「もう夕方の6時を過ぎてる」
「ゆ、夕方ぁ? なんで……あれ、なんか体が変?」
「今頃気付いたか。寒気とか、体が痛いとか、ねぇか?」
言われて初めて、絢子は寝苦しいのに気付いた。
「寒気はそんなにないけど、体が痛い。何だろ、息もちょっと苦しい」
「だろうな。俺らが来た時は、凄ぇうなされてたぜ」
ひたっと氷室の手が額に置かれ、その冷たさに絢子はウットリした。
「あ、冷たくて気持ちいい〜」
「ふん、少しは落ち着いたか? お前、体温計くらい常備しておけ」
「へ? 私、熱あるの?」
「凄ぇ熱かったぜ。お陰で、体温計と氷枕、買いに行く羽目になった。38度7分もあったんだぞ」
呆れたように話す氷室。絢子は目を丸くした。
「そんなに? ……あれ? じゃあ私学校は…」
「お前が無断欠席なんて珍しいからな。まさかと思ったが、部活の後で来てみりゃこの様だ」
「あ、ありがと斎」
「気にすんな。そんな殊勝になられると、却って気持ち悪ぃ」
「な、何よぉ。人がせっかく素直にお礼言ってんのに。……あ、部活、紫ちゃん一人で大変じゃなかった?」
「いや、結構張り切ってやってたぜ。お前のこと心配してた」
「そっか、悪いことしちゃったな」
「お前が気に病むこたねぇだろ。そう思うんなら、早く治せばいい」
「うん、ありがと」
絢子は少しつらそうな表情をする。氷室は眉をひそめた。
「話して熱が上がったかもな。ほら、体温計」
「ん…」
枕元に置いてあった電子体温計を受け取り、絢子は目を瞑って脇の下に挟んだ。
「口、開けろ」
「え?」
何だろう? と思う間もなく、薄く開いた口にカポッと何か差し込まれた。反射的にそれを舌で触ると、プラスチックの感触。
すると、先端に開いた穴から水のような物が流し込まれて、絢子はゴクッゴクッと嚥下した。冷たくて甘い味の水に、彼女の顔が美味しそうに笑う。全部を飲み干して、目を開けた。
「美味しい。何、これ?」
「ポカリ。熱出た時の水分補給は、水よりいいんだとよ。相模が言ってた」
その名前を聞いた途端、絢子の顔が泣きそうに歪む。
「相模……何か言ってた?」
「後で自分で訊けよ。今、雑炊作ってる」
「え!?」
それは、彼女にとっては衝撃的な言葉だった。
「え…何で、相模が?」
「俺が呼んだに決まってんだろ。俺じゃ料理は出来ねぇからな」
絢子が何か言おうと口を開き掛けたところで、タイミング良く体温計のアラームが鳴った。氷室が手を差し出したので、彼女は何も言わずに体温計を渡す。
「38度5分。また上がっちまったな。寒気は?」
「少し」
「寒気が治まるまでまだ上がるな。もうすぐ雑炊が出来上がるから、食べてから薬飲めよ」
「斎……」
体温計をケースにしまう彼を、絢子はじっと見つめた。目が潤んでいるのは、熱のせいだけではなかった。
「斎は知ってた? ……よね。相模が、卒業したらアメリカ留学するって」
「ああ、知ってたぜ」
絢子は唇を引き結んで更に目を潤ませた。
彼女がそれを初めて本人の口から聞いてから、ひと月近くが経っている。相模は全くと言っていい程変化はなかったが、絢子は彼に対してだけ妙にギクシャクしてしまい、周りはかなり心配していた。そんな矢先に、コレである。
「この前、相模に送らせたりしたのは、私のため?」
「まぁな。高城に告白されて、お前もやっと自覚してたから、ちょうどいいと思ったんだ。相模には、もう言ったのか?」
絢子が弱々しく頭を横に振る。そして、あの時のことを掻い摘んで話した。
「それで、留学のこと聞いたら頭真っ白になっちゃって。その後はよく覚えてないけど、そのまま相模は帰ったと思う。……知ってたんなら、教えてくれれば良かったのに。斎のバカ」
話しながら、絢子の目尻から涙が一筋こぼれる。
「本人から聞いた方がいいと思ったんだよ。熱はそのせいか?」
「分かんないよ。ずっと悩んではいたけど。……なんかさ、このまま言わずにいた方がいいんじゃないかって思って。相模は、今が一番大事な時だろうし、迷惑だろうなって…思っ……」
その後は嗚咽にまみれて、言葉にならなかった。熱があるのも手伝って、嗚咽は次第に本格的な泣き声に変わっていく。
普段から泣き言を言わない絢子にしては珍しいことだ。が、氷室は声を掛けることもなく、そっとベッドから腰を上げた。彼女はそれにも気付かず、泣き続けている。母親を亡くして以来、こんなに声を出して泣くのは、初めてのことだった。
ひとしきり泣いた絢子は、再び冷たい手が額に置かれたのを感じて、目を開けた。
「斎? ごめん、何か急に泣き入っちゃって」
「大丈夫か? 結城。氷室はもう帰ったぞ」
心配そうに自分を覗き込んでいたのは、幼馴染ではなく、彼女の想い人である相模だった。