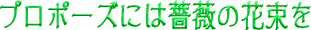一方、車を降りた朔は恋人の心理に気付くはずもなく、近付いてくる二人に笑顔で「やっほ〜、久しぶり!」と手を振った。
「あ? なんだ朔かよ」
彼女の顔を見た途端、隆輔は拍子抜けしたような表情で、逆立てた髪を掻いた。
「なんだ、って何だよ、リュウ」
「だってお前、いつも紅(あか)のRX-8で来るじゃん。ポルシェがあんな派手なドリフトかましてきたから、バトル気満々で来たってのにさ!」
「ま、相手がポルシェじゃ、隆輔の出る幕はなかっただろうけどな」
やんちゃ坊主の駄々をなだめるように、彼の肩を叩いて苦笑したのは、隆輔より5つ年上の真治だ。それでも年齢は朔とそれ程変わらない。
「ムッ、それじゃ俺が負けるみたいな言い方じゃないか!」
あからさまに口を尖らせた隆輔だったが、真治の言うことに外れはない。
「いくらチューナップしたからって、911ターボに勝てるか。恭輔ならともかく」
「あ、さっきすれ違ったぜ。相変わらず、いいテクしてるよな。あのコーナーで慣性ドリフト出来るの、恭輔くらいだろ」
「兄貴なら、どんな相手にも勝てるさ!」
「…………相変わらずブラコンしてんな」
隆輔の兄弟自慢に、げんなりしながら呆れたように朔が言った。この弟の兄貴自慢は、耳にタコが出来るくらい聞かされている。
「ところで朔。いつポルシェなんか買ったんだ? 君が財閥の御曹司なのは知ってるが、外車は買わないって言ってなかったか?」
「おんっ」
真顔で言う真治の言葉に、朔は絶句した。
殊更自分が女だと言ってはこなかったが、まさか『御曹司』にされていたとは!
『お嬢様』とも呼ばれたくはないが、まだ『令嬢』の方がマシだった。朔にとって『御曹司』というのは、職にも就かずに金を湯水の如く使い放題で遊び三昧、という定義なのだ。
「俺は、御曹司じゃない!」
「え? じゃあ何だよ?」
怪訝な顔で訊いて来る隆輔。そこへ、先程すれ違った白い車が、これまた甲高いスキール音と共に駐車場に滑り込んできた。そして隆輔の愛車の傍に、これまた見事なドリフトで停車して見せた。
それを見た朔は、面白くなさそうにその車を睨み付けた。自分と同じドラテクを見せ付ける彼に、少々ヤキモチをやいたのだ。
「朔!」
だが、後ろから聞こえてきた自分を呼ぶ声に、朔の顔は自然と綻んだ。それを見た真治は、真剣に驚いた表情でマジマジと彼女を見てしまった。今までこんな表情をする彼女を、見たことがない。
「真條。やっと来たか」
「やっと来たか、じゃありません。全く……」
「全く。なんだよ?」
ニヤニヤしながら訊いて来る朔を、彰人は恨めしげに見下ろした後、盛大に溜め息をついた。
「何でもありませんよ。それより、彼らは知り合いですか?」
さり気ない彰人の挑戦的な視線を受けて、隆輔は僅かに身構えた。目の前の彰人を上から下まで眺め、どう見ても走り屋には見えない彼のいでたちに、ムッと眉間に皺を寄せる。
「朔、こいつ誰だよ」
「えっと……俺の知り合い」
しばし言い淀み、朔はニカッと笑いながら、最も無難な紹介をした。しかし、彰人はそれが不満だ。横にいる朔の肩に手を掛け、彼女と親しいことを暗に見せ付ける。
「朔の婚約者です」
「しんっ」
「「こ、婚約者ぁー!?」」
真治と隆輔は、揃って目を剥いて大声を上げ、更に隆輔は余計な一言を口にした。
「お前、ホモだったのかー!?」
「誰がホモだー!! 俺は」
「朔は女性だよ、隆輔」
一人涼しげな声で朔のセリフを横取りしたのは、遅れてやってきた恭輔だった。癖のある色素の薄い前髪から覗く涼しげな目元。えらく男前な彼は女性によくモテるらしい。彼は悠然と歩いてきて、やんちゃな弟の隣りに並ぶ。
「じょせっ女!? 朔が!?」
「お前じゃ、気付かなくても仕方ないけど」
苦笑混じりで言われた隆輔は、「だって、どう見たって男じゃんか」と、何気に失礼なことを拗ねたように言って、プイッと横を向いた。
そんな弟を尻目に、恭輔の視線は彰人へと向き、自然と二人は睨み合う格好となった。
「初めまして、俺は時雨沢恭輔(しぐさわきょうすけ)。ここをホームにしているチームのリーダーで、朔とは走り屋仲間ですよ」
フッと余裕のある笑みを見せた恭輔に対し、彰人は完全に出遅れてしまった。不機嫌を顔に出すのは、明らかに年下であるこの恭輔の前では、敗北したような気になって面白くない。
「私は真條彰人。朔の婚約者ですよ」
挑発するつもりで名乗った彰人だったが、恭輔の方は全く意に介さず、朔に笑顔を向けた。
「それはおめでとう、朔」
周囲に女がいれば、たちまち黄色い悲鳴が上がりそうな、完璧な笑顔だ。見慣れている朔には、大した効果はなかった。
「おう、サンキュー! キョウ」
ピッと親指を立ててウィンクする朔は、そんじょそこらの男よりも男前だ。
恭輔は溜め息を隠せなかった。
こんな男前の女でも結婚願望があって、その上でしっかり男前をキープして婚約にまでこぎつけたのだから、世の中は不思議なものである。そして隣にいるその婚約者と言う男。どう見ても『御曹司』という言葉が似合いそうな……しかしそれなりに歳は食っている、そんな男が今更朔のような女性に惚れるとは、彼にとっては世界七不思議にも相当した。
もし彼女が誰にも取られなかったら、いすれ自分がプロポーズしようと思っていた。しかし、今の朔は幸せそうなオーラを放っている。本人は気付いていないだろうが、そのオーラが男装でも彼女が女性であると、しっかり主張しているのだ。それが分かったからこそ、素直に出た祝いの言葉だった。
恭輔は内心の葛藤は他所に置き、彼女の乗ってきたポルシェに目をやった。
「ところで、なんで今日は911なんだ?」
「ああ、あれはこの真條の車なんだけど、一度ポルシェで峠走ってみたかったんだよ」
「なるほどね」
外車でドリフトしてみたい、と以前から喚いていたのは、彼も知っている。朔がGT2をキャッシュで購入できる身分であることもまた、彼はよく理解していた。自分で買えばいいと言ったのは、いつだったか……。
「911ならGT2にすればよかったのに」
「俺が買った訳じゃないし、そこまで我が儘言うのもなぁ…… ターボでも十分飛ばせたぜ」
「そりゃあ腐ってもポルシェだからね」
その持ち主がすぐ傍にいるというのに、朔も恭輔も言いたい放題である。
彰人はポーカーフェイスを装っているが、内心は恭輔に対して腸が煮えくり返っていた。
なんで初対面で、こうも不躾なことを言われなければならないのか! 大体、朔と知り合いというだけでも気に入らないと言うのに……。日頃会っている学園の同僚ならともかく、いきなり出てきて朔と親しげに話していること自体が、彰人の神経を逆撫でしていた。しかも、恭輔の方は確信犯であることは、彼の目を見れば明らかだ。
「なぁ兄貴。兄貴なら朔のポルシェとやって勝てるか?」
それまで蚊帳の外だった隆輔が、車の話になったところで興味津々で訊いてきた。自分では無理と真治に言われたばかりだが、自分より遥かに経験と腕のある恭輔なら勝てると思っての問いだ。
だが、返って来たのはニヤニヤ笑いの曖昧な答えだった。
「さぁね、外車とはまだやったことないし、相手が朔だからねぇ」
「んじゃ、やるか? 元々走るために来たし、お前がいるんなら好都合だよ」
嬉々として提案する朔の目は、既にバトル気満々である。
「そうだね、いいよ。朔の婚約祝いに、本気の勝負してみようか?」
「やりぃ!」
「朔……」
完全に置いてけぼりを食らっていた彰人は、ようやく口を挟む機会を得た。しかし、その表情は非常に苦々しいものだった。
「なんだよ、真條」
「もう目的は果たしたでしょう」
「まだだよ! せっかくキョウが勝負してくれるってんだぜ! やらずに帰ったら女が廃る!」
ポルシェに向かおうとする朔の腕を、彰人は強引に引き戻す。
「朔!」
「何なんだよ、さっきから! 真條の車を借りるのは悪いと思ってるけど、こんな機会滅多にないんだぜ!」
「車はいくらでも貸しますよ」
「だったらいいじゃないか! まだキョウに本気の勝負してもらったことないんだ。俺にやらせろよ! バトルのこと何も知らないくせに、口出しするんじゃねぇよ!!」
掴まれていた腕を振り解いた朔は、彰人が今まで見たことがない程に憤慨していた。その怒りに圧され、彰人は何も言えずに彼女を見下ろした。
恋人同士の間で微妙な空気が流れ始めた頃、絶妙なタイミングで恭輔が口を開いた。
「朔、一回練習してくれば? まだ一度もあれでドリフトしてないだろ。クラッチのタイミングやハンドル回りがいつもと違う。一度慣らした方がいいよ」
恭輔をしばらくジッと見た朔は、何も言わずにポルシェへと歩いていき、彰人には目も繰れずに車に乗り込み、あっという間に走り去って行った。
「真治、みんなにバトルするって通達してくれ」
「分かった。けど……大丈夫か?」
「兄貴なら勝つだろ!」
真治の問いを自分勝手に解釈し、隆輔はそう言い残して一箇所に集まりつつ仲間たちの元へと駆けて行った。
「はぁ、全く、我ながらおバカな弟だよな……。真治、頼む」
「ははっ、分かった。じゃあ、健闘を祈る」
右手を挙げて隆輔の後を追う彼に、同じく右手を挙げて応じた恭輔は、一つ息を吐いたところで彰人に視線をくれた。
朔に邪険にされてから石化していた彰人は、恭輔と二人きりになったところで、ハタと正気付いた。露骨に不機嫌な表情で、傍にいる彼を見る。
「バトルとは何なのです?」
「朔から聞いてませんか? お互い車に乗って、ゴールにどちらが早く到着するか、競うんです」
「それは聞いていますが……危険はないのでしょうね?」
実に真剣な表情で訊いて来る彰人に、恭輔は笑いを噛み殺した。
「俺と朔なら、先ず危険はありませんよ。車の運転に、絶対安全、なんて言葉はありませんが、それでも俺と彼女なら何か起きても対処出来る」
釈然としない彰人を見やり、恭輔は再び口を開いた。
「それよりも、訊きたいことがあるんじゃないですか?」
「な、なにを……」
「どうして朔とそんなに親しいのか?」
ズバリ、言い当てられて、彰人が言葉に詰まる。恭輔は溜め息をつきつつ腕を組んだ。
「さっきも言いましたけど、朔とは走り屋仲間なんです。俺はチームを率いているけど、彼女は一匹狼で、色んな峠に顔を出しては好きに走り込んだり、たまに地元のチームとバトルしたりしていたそうですよ。お陰で、走り屋仲間では『紅いRX-8』と言えば、朔を指す言葉になりました。朔と知り合ったのは3年前です。たまたま俺がいない時に、弟の隆輔がチームを掛けて勝負をしたらしくて、『負けた!』って俺に泣き付いて来たんです。それで勝負せざるを得なくなってしまった。結果は同時にゴールという、俺にとっては負けに等しい勝負でしたよ。それ以来の付き合いです」
彰人が聞く限り、サラリと言った恭輔の口調には、特に特別な感情が宿っているようには感じなかった。やや安堵した彰人だったが、それを見越したように恭輔は意味深な視線を送りつつ言葉を続ける。
「朔は男にしか見えなかったから、ちょっと油断していたな」
彰人は、その言葉の裏を敏感に感じ取った。普段は見せない剣呑な光を瞳に宿し、恭輔を正面から睨み付けた。
「どういう意味です?」
「朔を愛する物好きな男は自分だけだと思ってた、ってこと。まさか、こんな伏兵がいたとはね」
「それはこちらのセリ」
「それも、こんなオジサンが彼女の好みだったなんて……はぁ」
肩をすくめ、両手の平を天に向け、恭輔は至極残念そうな顔で言った。『オジサン』呼ばわりされた彰人は、ショックと怒りで声も出せない。朔と同い年の恭輔にとっては、10歳年上の彼は立派に『オジサン』である。勿論、朔を取られた腹いせであろうが……。
「俺の方が早く知り合っていたのに、まさかこんな形で掻っ攫われるとは、思ってもいなかった」
「知り合っているなら、私の方が早いですよ! 彼女が教員として赴任して来てからの付き合いですからね!」
年甲斐もなく声高に言う彰人を軽くいなして、恭輔はうっすらと笑みを浮かべた。
「年下の俺相手に、何を熱くなっているんです? あなたはもう婚約をしているのですから、何の心配もいらないでしょう。それとも、彼女のただの知り合い相手にヤキモチですか?」
ただの、という部分を殊更強調した恭輔だったが、それがわざとであることは、その表情を見れば分かる。思わずカッとなった彰人には目も繰れず、恭輔は駐車場の入り口に視線を向けた。
直後、朔の乗ったポルシェが駐車場に滑り込んでくる。先程とは違って、静かに停車した車から、彼女がご機嫌斜めな顔で降りてきた。
「朔!」
すぐさま駆け寄る彰人を、何故か朔は睨み付けた。
「さ、朔?」
「真條!!」
「はい……」
「何なんだよこの車! ドリフト、スッゲェやりにくいぞ!!」
「…………」
恋人の思わぬ剣幕に、彰人は困惑した表情で黙り込んでしまった。車など『走る物』としか考えられない彼には、朔の言うことが全く分からない。
「朔」
そこへ、当然の顔をして恭輔が近寄ってきた。
「その911ターボは、朔がいつも乗っているRX-8より車両重量が200キロ近く重いんだ。いつものつもりでステアリングしても、感覚は大分違うはずだよ」
「むぅ……じゃあどうすりゃいいんだよ! このままじゃキョウに勝てないじゃん!」
「一度走ってきたんだから、朔ならもう問題ないと思うけどね。心配なら……」
恭輔の話すアドバイスに熱心に耳を傾けている朔は、彰人がこれまで知らなかった顔をしていた。二人の話に全く付いていけず、疎外感を味わう彰人。
「兄貴と朔の会話には、俺も付いてけねぇよ」
背後から慰めらしき言葉を掛けられ、彼はどんよりした表情で振り返った。
弟の隆輔が、つまらなそうな顔で両腕を頭の後ろで組みつつ、立っていた。
「二人の話は高度過ぎて、俺みたいな実践派にはつらいんだ。気にすんなよ」
彼はそれでもいいだろうが、彰人にとってやきもきする今の状況は耐え難い。しかし、こんなところで取り乱すのは、彼の自尊心が許さなかった。努めてポーカーフェイスを装いつつ、二人の真剣な話し振りを眺めている。
「あんたさぁ、いいとこのボンボンだろ。朔とはそっちの関係な訳?」
「どういう意味です?」
ボンボン、という言葉が癇に障り、睨むように隆輔を見た。睨まれた方は、何処吹く風だ。
「見合いとか?」
「朔とは同僚です」
「へぇ! 朔も教師には見えねぇけど、あんたも別の意味で教師っぽくねぇよな。働かなくても困らねぇんじゃねぇの?」
「君に関係ないでしょう。くだらない会話しか出来ないのなら、黙っていてもらえませんか?」
取り付くしまもない言葉に隆輔が肩をすくめた時、彰人は何を思ったのか、朔の方へと歩みを進めた。
「え!? おい、どこ行くんだよ?」
「私の車です。同乗する権利はあるでしょう」
聞く耳持たずに行ってしまった彰人の背中を、隆輔はポカーンと見送った。
「は!? 同乗って、これからバトル……ったく、これだから素人は。どうせ朔に怒鳴りつけられるだけだって」
果たして、彼の予想は的中した。
当然の顔をしてナビシートのドア手を掛けた彰人が朔に咎められ、
「体重70キロのお前に乗られたんじゃ、それだけで遅くなるだろ! こっちはキョウの車体よりずっと重いんだぞ! 乗せられるかバーカ!!」
と罵倒されていた。
あからさまに落ち込む彼の背中を見るに見かねて、隆輔は傍まで言って肩に手を置き、声を掛けた。
「朔はバトルの前で気が立ってんだよ。走る前は、いつもあんな感じだぜ。バカって言われただけじゃん、気にするなって」
しかし、そんな親切心の慰めも、彰人には届かなかったようだ。
「バカ……この私がバカと言われた。しかも長音符号付きで……」
ちょーおん符号というのが何なのか、隆輔には分からなかったが、自分より10コ以上は確実に年上だろう男に、さめざめと泣かれるのは鬱陶しいなぁ…… と、遠い目をした。