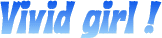残されたのは絢子と相模。
氷室が二人に気を遣ってくれたのだが、話すというだけで、場所や行き先を決めていなかった二人は、相模の提案で絢子のマンションにやってきた。
「ホントに大丈夫なの? ウチって相模んちとは逆方向じゃん」
「帰りが遅くなって、もし結城の身に何かあったら、俺が氷室に恨まれる」
真剣な表情で言われ、絢子は笑い飛ばした。
「あははっ、大丈夫だよ。いくら幼馴染だからって、相手は私だよ。斎はそんなことしないって」
「そんなの分からないだろ。結城のことになると、氷室は俺たちに厳しいからな」
初耳のことで絢子は目を丸くした。
「え、そうなの?」
「そういう訳だから、結城の家の方がいいんだよ」
「でも、私は相模の体の方が心配だけどね。なんかボーッとしてるよ?」
「そうか?」
絢子の目には、相模は今にも倒れそうに見えるのだが、本人は相変わらず鈍感なのか、自分の状態が分かってないらしい。
まぁ、自分のマンションなら何かあっても大丈夫か……と彼女は楽観的に考え、相模と共に会場を後にした。
**********
真夏のマンション内は、夕方ともなるとサウナのようになる。
絢子は、着いてすぐに冷房を入れた。ひんやりとした空気が部屋を満たしていく。
「ふぅ、暑いねぇ。今冷たいお茶淹れてくるから待ってて」
相模をリビングのフローリングに座らせ、絢子はキッチンから冷たいウーロン茶を持って来た。
クーラーの涼しい風がそよぐリビングで、しばし涼み、絢子は隣りであぐらをかいている相模を見た。
「それで、話って」
問われ、相模は持っていた空のコップをテーブルに置いた。
「結城に告白されてから、俺自身色々考えてみたんだ。結城のことは好きだけど」
相模がサラッと言ってのけたので、絢子は思わず聞き返した。
「え!?」
「だから、結城のことは好きだけど」
「ええぇ!?」
顔を真っ赤にして叫ぶ絢子に、相模はため息をついて付け加えた。
「話は最後まで聞け」
「う、うん。ごめん」
相模の言葉に素直に返事をしたものの、絢子は心臓が爆発しそうなほどドキドキしていた。
「結城のことは好きだけど、それは異性としてっていうよりも、人間として好きなんだと思うんだ。この前……結城が熱出した時に、ここで氷室に言われた。人間として好きなら、付き合うには十分な理由だって。それで俺なりに考えてみた」
一旦口を閉ざし自分を見つめる相模を、絢子は固唾を飲んで見守った。
「な、なに?」
「俺は3月に卒業したら、アメリカに渡る。たとえ今回受けた試験で入学許可が取れなくても、卒業後には向こうに行く。だから」
「だ、だから?」
「付き合ったとしても卒業したら別れることになる。別れなきゃいけないことが分かっていても、結城は平気なのか?」
真剣な表情で再び口を閉ざした相模。絢子はしばらく絶句し、眉をひそめた。
「え……それって、相模は私と付き合ってくれるってこと?」
「結城がそれでもいいなら」
相模は平然と言い切り、絢子は口を開けて彼を見上げた。
「あの、私のこと好きってホント?」
「本当だ。嘘を言ったって何にもならないだろ。それが恋愛感情かどうかは分からない。でも、結城のことは嫌いじゃないし、いい子だと思う。むしろ、結城が俺を好きだってことの方が不思議だよ。てっきり氷室と出来てると思ってた」
とんでもない勘違いに、絢子は慌てて口を挟んだ。
「ちょっ、なんでそんな風に思われちゃう訳!? 私と斉はただの幼馴染みさね」
「ああ、氷室も結城のことは家族だって言ってたしな」
「……だったら、なんでそんな誤解」
「でも氷室は結城が好きなんだよ。俺はそう感じる。まぁ、そう感じるようになったのは、ここ一月くらいのことだけど」
「ひとつき……」
絢子は呻く様に呟いた。それはつまり、彼女が相模に告白してから、ということになる。
「正直言って、どうして俺なのかと思った。あの時、言い掛けたのは」
「え、あの時って」
「結城が熱出した時、返事を止められただろ」
その時のことを思い出したのだろう。絢子の顔がサッと朱に染まる。恥ずかしいのか俯いてしまった絢子を、相模は微笑を浮かべて見た。
「あの時は、断ろうとしたんだ。本来なら部活はもうやっていないはずだった。部活をやりながら、留学の試験を受けるのは無謀なことだと、誰からも言われていたから。それを氷室だけが、部活をやめないでくれって言ったんだ。自分が出来るだけのサポートはするから、来年全国大会で優勝するまで、部活を続けろって」
あまりにも淡々と話すので、絢子は唖然としていた。
「け、結構ムチャクチャな事言ってたんだね、斎。それで、続けたんだ。相模は」
「ん……でも、すぐには決められなかった。氷室には悪いと思ったが、あの頃は留学とバスケと、どっちが大事かと訊かれたら、留学の方だったから」
「当時は? …ってことは、今は違うの?」
絢子の当然な指摘に、相模は笑って言った。その表情には、どこかスッキリしたものが垣間見える。
「今は、どっちも大事なんだ。氷室がバスケ部に引き止めなかったら、俺はおかしくなってたかもしれないし」
「え……どゆこと?」
不穏当な発言に身を乗り出して訊いてくる彼女を見て、相模は苦笑をもらした。
「TOEFLとSATを日本の現役高校生で受験するのは、思ったよりもしんどい。学園での成績も重要なファクターだから、おろそかに出来ないし。両立は確かに難しかったけど、部活がいい息抜きになった。部をやめるなって言われた時は、氷室を恨んだけど……いやつい最近までそうだったけど、今は続けてよかったと思ってる」
「でも、大変だったんじゃない?」
「そりゃあね、息抜きになるとはいえ、副部長の仕事は多いし、事情を知っていても氷室は手加減しないし」
氷室を困った奴のように話す相模だが、その顔は心なしか嬉しそうだ。
「まぁね、あいつもバスケのことになると、妥協しないから。……それで、どういう経緯で気持ちが変わったのさね?」
「結城が熱出した時に、氷室に言われたんだ。たとえ別れることが決っていても、俺と付き合ったという事実は結城にとって思い出になるって。その時は、これ以上俺に期待しないでくれって、俺も怒鳴ったりしてさ。久し振りに氷室と険悪になったよ。だからかな、そういう事情でも結城が構わないなら、付き合ってみようって思ったんだ」