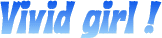しばらくして玄関の鍵を開ける音がして、相模は顔を上げた。大きなスポーツバッグを肩に掛けた氷室が、リビングに入ってきた。
「来たぜ」
憮然とした表情で鞄を床に置き、何故か偉そうにのたまう。相模は溜め息でもって迎えた。
「絢子はどうしてる?」
「あれ以来見てない」
氷室がドアを開けて覗くと、彼女は背中を向けてベッドに寝ていた。そっと近付いて覗き込むと寝息が聞こえ、額を触ったがそれ程熱はないらしい。
ホッとしてリビングに戻ってきた氷室は、相模の前にドカッと座り、胡座をかいて彼を睨み付けた。
「それで、お前は絢子に何て返事するつもりなんだ?」
「……俺は卒業したらアメリカに渡る。春休み中だが、向こうの生活に慣れておきたいからな」
「つまり、絢子とは付き合わないってことか?」
「その方が結城のためだろう」
「なに?」
淡々と語る相模を、氷室は片眉を上げて睨む。
「俺は来週にはTOEFL、来月にはSATを受ける。その間バスケの大会があるし、終わった後は結城の方が進学で忙しくなるだろう? 恋愛にうつつをぬかす余裕なんかないはずだ。それに、もし付き合ったとしても、一緒にいられるのは精々半年程度だ。そんなの酷いじゃないか」
「絢子に?」
「他に誰がいる」
きっぱりと言い切る相模の目を見て、氷室は口を噤んだ。溜め息をつき、右手で首の後ろをさすっている。
「お前さぁ、生真面目に考え過ぎだって。たった半年でも、恋人として付き合えることが、あいつにとってどれだけ幸せなことか、考えてみろよ」
だが、相模は目を瞑り諦めの表情で首を振った。
「相模」
「電話でも話しただろう。これ以上俺に期待するのはやめてくれ。正直言って、勉強と部活だけでもういっぱいいっぱいなんだ。今の俺には、彼女のことまで気に掛ける余裕がない。お前にとって結城が大事なのは分かるし、彼女が俺に好意を持ってくれているのも、嬉しく思う。でも、ダメなんだ」
頑固な相模に溜め息をついた氷室だったが、ふと思い付いて訊いてみた。
「なぁ、今までのお前の言ってることを総合してみると、絢子のことを嫌ってる訳じゃないのか?」
「? 別に嫌いじゃない。結城を嫌いな人間なんてそうはいないだろう。いい子だと思うぞ」
「あー……そうじゃなくて、絢子のこと、好きなのか?」
氷室がそう訊くと、相模は首を傾げ、しばし考えた。
「……そうだな。好きだよ」
あっけなく認めた相模を、氷室は口を開けて見つめた。
「お前…だったら何の問題もねぇじゃねぇか!」
「あぁ……いや、そういう意味じゃなくて」
のほほんと話す相模に、氷室はギリギリと歯軋りしている。
「彼女に対する気持ちが、恋愛に通じるのかと問われたら、多分違う」
「多分て何だよ!」
氷室の怒鳴り声を、顔をしかめて聞き流し、相模は続けた。
「よく分からない。ただ、結城が女子だからとか、そういう対象じゃなくて、人間として好きなんだと思う」
氷室はがっくりと肩を落としてうなだれた。
「それでいいじゃねぇか。付き合うには、十分な理由だぜ」
「だから、それは出来ないと言ってるだろう」
「どうして! 試験が終わってからでも付き合えばいいじゃねぇか」
「だからそれは」
「別れる時に絢子が可哀想だなんて言うな! お前と付き合ったことは、あいつにとって掛け替えのない思い出になる。なんでそう考えてやらないんだよ!」
「考える余裕なんかないって言っただろう。とにかく、もう俺のことは放っておいてくれ!」
彼らしくない怒鳴り声を上げて、相模は立ち上がった。そして、床に置いてあった鞄を持ち上げる。が、氷室がその鞄を押さえた。
「氷室……離せ」
「とりあえず座れ」
「氷室!」
普段は言い争ったりしない二人だが、この時ばかりはどちらも譲らなかった。
「全く、頑固に考えすぎだ。来月に試験が終わるんだったら、その後で絢子とちゃんと話せばいいじゃねぇか。絢子が返事はいいって言ってんなら、1ヶ月くらいは保留にしていても問題はねぇし」
「そんなこと……」
「絢子に悪いとか言うなよ。嫌いじゃないのに、理由もなく振る方がもっと酷いんだからな」
「…………」
氷室のその言葉に、相模は押し黙った。
「なにも今すぐ何かしろって言ってんじゃねぇんだ。今まで部活と勉強を両立させて来たじゃねぇか。勉強の方は、俺だってサポートして来たし。絢子のことだって、サポートするぜ」
「…………分からないな」
「何が?」
「なんでお前は、そこまで結城に肩入れするんだ? 幼馴染って理由だけじゃ、ないんじゃないのか?」
彼の言外の意図を悟った氷室は、神妙な顔をして、再度座るように床を指差した。自分から訊いたことだったので、仕方なく相模はそれに従った。
「お前さぁ、俺が絢子を好きだと、思ってんだろ」
核心を突いた言葉に、相模の目が細まる。
「違うのか?」
「違う。高城もそう思ってたみたいだが、違んだよ」
「どういうことだ?」
訝しむ相模に、彼は苦笑いを見せた。
「俺にとって絢子はさ、家族なんだよ。生まれ月はあいつの方が早いから……姉貴になるのか。それはちょっと気に入らねぇが、俺が生後間もない頃に、あいつは俺の周りをよちよち歩いてたんだぜ。そんな時からの付き合いなんだよ。だから、恋愛感情なんて持ちようがないし、絢子も俺のことは家族みたいに思ってるさ。血も繋がってないから、みんな誤解しがちだけどな」
「…………」
「別に何が何でも絢子と付き合え、とは言わねぇよ。でも、あいつはお前に恋してんだ。男共が着替えしてる部室にズカズカ入ってくるような、恥じらいの「は」の字も持ち合わせてなかった女が、お前の着替えを見て挙動不審に陥って、その上、恋心を持て余して熱まで出してんだぜ。今すぐとは言わねぇから、試験が終わったら、絢子のこと考えてやってもいいんじゃねぇか?」
相模は、黙ったまま氷室から視線を逸らし、無表情に床を眺めていた。
「やっぱり帰るんだ?」
それから暫くして、相模は腰を上げた。今度は氷室も止めずに玄関で見送る。バッシュを履いた相模は、鞄を肩に掛けて言った。
「お前がいれば、結城は大丈夫だろ? 帰らないと、親が煩いからな」
「……なぁ、お前がアメリカに留学するのって、日本でのしがらみを絶ちたいからとか、そんなんじゃ、ないよな?」
氷室の懸念な問いに、相模は静かに笑った。
「違うよ、そんなんじゃない。そんな理由だったら、いつまでもこの学園にはいないさ。……そんな風に見えるのか?」
「まぁな。お前って、そういうところは容赦ねぇだろ」
ズバッと痛いところを突いた様な氷室の言葉だったが、言われた本人は首を傾げただけだ。
「……と言うより、淡白なんだろうな、人間関係に対して」
ならば、6年間も部活を続け、ストリートバスケにまで付き合ったその理由は……問いかけようとして、氷室は止めた。今、聞きたいことは、そのことではない。
「じゃあ、なんでそんなに留学したがるんだ? 冬泉じゃなくても、日本の大学を出てからだっていいんじゃねぇのか?」
不思議と、これまで二人の間で出なかった話題だ。考えてみれば、何も茨の道を自ら進む必要はないのだ。1年でも2年でも、日本で大学生をやってからでも遅くはない。
だが、相模は否定した。
「相模?」
「尊敬する教授が、向こうの大学にいる。どうせ受ける講義なら、その教授から直接受けたい。理由はそれだけだ」
予想もしていなかった返答に、唖然とする氷室を残して、相模は出て行った。
しばし固まっていた氷室は、溜め息をついて前髪を掻き揚げた。
「それだけの理由で現役留学するって? 相模って分かんねぇ。こりゃ絢子の恋路も、前途多難だぜ」