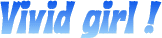「変なこと考えたから、また熱上がっちゃったかな……。今までこういうことで悩んだことって、なかったもんね」
つくづく自分が心を持て余していることに溜め息をつき、モソモソとベッドに入った。薬の作用でウトウトしていると、相模がノックをして静かに入ってきた。
ひたっと額に触ってくれる手が、冷たくて気持ちいい。
「大丈夫か? 結城」
「うん、相模の手が気持ちいいよ」
薄く目を開けた彼女の顔は、少し赤く熱っぽい。相模は眉をひそめた。
「また少し熱が上がったかもな。計ったか?」
「まだ……」
彼は溜め息をついて、枕元にあった体温計を絢子に渡す。
「計った方がいい。ほら」
「うん、ありがと」
布団の中でモゾモゾ動いて、それを脇の下に挟んだ。
「あのさ、相模」
「うん?」
熱のせいか、火照った顔を覗かせる絢子を見下ろしながら、相模がベッドの傍の床にあぐらをかいた。
「あのね……は、話があるの」
一大決心で言ったのだが、相模は難しい顔をした。
「今はやめた方がいいんじゃないか? かなり熱っぽい顔をしてるぞ」
「でも、話さないと多分下がらないよ、この熱」
「そういうのは、俺よりも氷室に話した方が」
「相模じゃなきゃ駄目なんだってば!」
彼の戸惑う言葉を遮り、泣きそうな顔で叫ぶと同時に、体温計のアラームが鳴る。絢子は液晶に表示された体温を見て、相模に渡した。その彼はと言えば、絢子の剣幕に面食らったが、出された体温計を見て表情を曇らせた。
「38度4分か。氷枕を換えてやるから、静かに寝ていた方がいいぞ」
「もう寒気はしないから、大丈夫だよ。それよりも話を聞いてよ」
頭の下にある、タオルに巻かれた氷枕を外そうとする彼の手から逃れるように、絢子は体をずらした。
「結城」
「聞いてもらえなきゃ、結局この熱は下がらないよ。そういう熱だもん。もう、このままこの気持ちを、自分の中だけに留めておくことが出来ないから」
今まで見たことのなかった、絢子の切なげな表情に彼は困惑した。
「結城?」
「私、相模が好きなの」
「…………」
彼の肩がかすかに揺れた。無表情に、絢子の告白に耳を傾けている。
「でも今は、多分相模にとって一番大事な時期だろうから、言ったら迷惑だろうなって思ってて。色々悩んでたら、こんな熱なんか出ちゃったし。もう、どうしていいか分からなくて……ごめん、結局言っちゃった」
彼を見上げる絢子の目から、ポロッと涙がこぼれた。
「お母さんのこと思い出したから。このまま言わなくて、もし永遠に別れるようなことになったら、すごく後悔するって思った。でもこれは私の勝手な気持ちで、相模の事情は考えてない。我が儘だって分かってるけど、このまま言えずに悩んでいても熱は下がらないし、却ってみんなに迷惑掛けるって思ったから……」
絢子の告白を黙って聞いていた相模は、しばらく無言で彼女を見つめ、そして、ふいと顔を逸らせた。
「結城、俺は」
「返事はいいの。今は、自分の気持ちを伝えたかっただけだから。本当に、今は自分ことしか考えられなくて。ごめん……」
絢子はそれだけを言い、布団の中で体の向きを変た。もう、まともに相模の顔を見ることが出来なかったのだ。
一方、言おうとした言葉を遮られた相模は、絢子が背中を向けるのを見て、静かに息を吐いて肩を落とした。そして、自分から背を向けたままの絢子の頭に手を伸ばす。
「結城、氷枕替えてくるから、頭を上げてくれ」
「いらない。十分冷たいから、これでいいよ」
頑なに頭を上げようとしない絢子に、相模は諦め顔で溜め息をついた。
それきり彼女が何も言わないので、彼はそっと立ち上がって部屋を出て行く。絢子は布団の中で、声を殺して泣いた。
**********
居間に出た相模は、大儀そうに息をつき、鞄の傍に座った。初夏のこの時期、フローリングの床はひやっとしていて、気持ちがいい。
彼は立てた膝に肘を乗せ、しばらくの間思案した。そして鞄から携帯を出し、ある番号を押した。5~6回の呼び出し音の後、相手が出た。
『相模?』
「氷室……今いいか?」
繋がったことに安堵した相模の声を聞いて、氷室は怪訝そうに訊いた。
『どうした? 絢子と何かあったのか?』
『絢子に』と言わず、『絢子と』というセリフに、相模はピンときた。
「お前、用事ってのは嘘だな」
呆れて溜め息混じりに言われても、電話の向こうの声は動揺した様子もなく続けた。
『ああ、今自室にいる』
「全く、よくそんなしれっと言えるな。結城が心配じゃないのか?」
『まぁ、お前がいるからな。それでど』
「夜はどうするつもりだったんだ!? 結城を一晩放っておく気だったのか」
『だから、お前がいれば大丈夫だって』
「氷室……」
相模は、空いている方の手で頭を抱える様に下を向き、大きく息を吐いた。
「他人の俺が、結城と一晩一緒にいられる訳がないだろう。用事がないなら、すぐに来い」
『えー、面倒臭ぇからやだ』
「おまっ! 幼なじみだろう。とにかく……」
『? なんだよ?』
一旦言葉を切ったのを、氷室が訝しく問うと、彼は再び続けた。
「話がある。すぐに来てくれ。俺は帰らなきゃならないから、お前泊まれる準備してこいよ」
『話なら明日でもいいだろ。いいから、お前が絢子の傍にいてやれ。じゃあな〟
さっさと通話を切ろうとする気がミエミエだったので、相模は切られる前に、畳み掛けるように言った。
「なんでそこまで俺を結城の傍にいさせるんだ?」
『深く考えるなよ。絢子にとっちゃ、俺よりお前の方がいいんだ』
煮え切らない氷室の言い方に、相模は腹の底がすぅっと冷えるのを感じた。次に彼の口から出た声は、普段穏和な相模からは想像も出来ない程、冷ややかなものだった。
「それは、結城が俺を好きだからか?」
『……ああ、あいつ、やっと告白したんだ』
どこか茶化したような口調に、相模の腹の中はますます冷えていく。
「ふざけるな。この前から、やたらと結城と二人きりにしたがったのは、」
『ああ、絢子がお前を好きなの知ってたし、高城に告白されてから、お前のことを男としてに意識するようになってたからな。いい機会だと思ったんだよ。まさか、絢子が恋煩いで熱まで出すとは、思ってもいなかったけど……』
最後の言葉は茶化した口調だったが、幼馴染を案じる響きが聞き取れた。
「とにかく、携帯で話していても埒はあかないだろ。こっちに来い」
『その必要はねぇよ。お前が付いていてやれ。着替えが必要なら、明日朝に俺の制服持って行くから』
「お前な、そういう問題じゃないだろう」
果てしなく平行線な話に、相模の声音は更に冷気を増す。氷室は逆に声を荒げた。
『相模。悪いが、俺は絢子の味方なんだ。あいつを泣かしたくはないし、あいつの望みは叶えてやりたいんだよ』
「それは立派な心掛けだがな、俺はどうなる?」
『だから、「悪い」って言ってるじゃないか!』
苛立つ氷室に対し、相模は氷を含んだような、冷静な口調を崩さない。
「何にしろ、結城のためだと思うなら、こっちに来いよ。今の結城には支えてやる奴が必要だ。それは俺じゃない」
『どうして? 告白されたんなら、返事はしたんだろ? 絢子が告白してそれっきりなんてことは、ないはず…』
「してない」
言葉尻を遮るような相模の即答に、電話の向こうで絶句する気配がした。
『……は!? してないって』
「俺は言おうとしたが、結城が返事はいいと言って、俺から顔を逸らした。だから、彼女に何も言ってないし、お前が想像しているような展開もない。これで分かったろ。すぐに来てくれ。頼むから……これ以上俺には何も期待するな。去年の全国大会が終わった時点で、退部したかった俺を引き止めたのはお前だ。留学の準備のためだと言っても、お前は聞き入れてくれなかった。副部長として支えてほしいと言ったよな。俺は原田を推したのに。あいつなら……いや、もう何を言っても今更だ。とにかく、俺がここにいる理由はない。お前がいるべきなんだ。いいな、すぐに来いよ」
相模は念を押すように言って、携帯の通話を切った。たたんだ携帯を手に、立てた片膝を抱くようにして、頭(こうべ)を垂れた。疲れたような溜め息が、その口をついて出る。
「はぁー……これって結城を泣かすことになるのかね。氷室に怨まれそうだな」
灯りも点いていない暗い部屋で、相模は頭を抱えるように俯いていた。