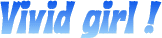レギュラー専用の部室では、この後に寄るファーストフードをどこにするかで、揉めていた。
「絶対、絶対、マッ○! クーポン券がある上に、通常価格も断然安い!」
そうきっぱりはっきり言うのは、レギュラーではないはずの絢子。なんで彼女がここにいるんだ? と言う疑問は、男子バスケ部には愚問である。
「俺はケン○ッキー! 肉が食いてぇー!」
「高城! ケン○ッキーなんかバカ高いじゃないの!」
「でもよぉ、質と量はやっぱケン○だよなぁ」
思わぬ高城への援護射撃は、原田。
「でも、ケン○ッキーはやっぱり高いですよ。安く済むところの方がいいような気がしますが・・・」
「金井! よく言った!」
自分より背の低い後輩レギュラーの背中を、絢子はバンバン叩く。そのあまりの勢いに、相手が咳き込んでいても、お構い無しである。
「俺はファー○トキッチンなんか好きだぜ」
「あれのどこが好きなのさね!?」
「ベーコンエッグバーガー。玉子とベーコンが美味いんだよな」
その味を思い出してか、多少うっとりとした顔をしたのは、桂木だった。
「そんなの、マッ○だって食べれるじゃない!」
「あそこは期間限定でしか食えねぇじゃん。だからダメ」
「う〜〜〜松永! あんたは!?」
少々うんざりした顔で聞いていた松永は、突然話を振られて面食らった。
「え……俺? 別にどこでもいいよ。ファーストフードなんて、どこでも一緒じゃんか」
「「「「それは激しく違う!!」」」」
高城、桂木、絢子、原田から激しくツッコミをされ、松永は目を白黒されてタジタジとなった。そこへ口を挟んだのは、氷室部長だ。
「もうどこでもいいじゃねぇか。大体、なんで絢子がしゃしゃり出てくんだよ!」
「何言ってんの! 今日、あんたたちが雑多なことを気にする必要もなく、バスケの練習に打ち込めたのは、誰のお陰よ! 今日だけじゃないわよね、い・つ・も! それは私と紫ちゃんが一生懸命働いたからでしょうが! そんな私たちを労うのは当然でしょう? 別に奢れって言ってんじゃないんだから、いいじゃない!」
言いたい放題だが、確かに彼女の言う通りでもあるので、誰も反論が出来ない。紫ちゃんとは、絢子以外の唯一のマネージャーで、後輩に当たる2年生だ。その彼女は、居心地が悪そうにドアの前で鞄を持って立っている。
「あの……あたしは帰りますから。皆さんで行って来て下さい」
「ダメよ、紫ちゃん! こういう時はちゃんと主張しなきゃ! 大丈夫、紫ちゃんの分はこいつらに出させるから!」
はぁ!?
寝耳に水のレギュラー全員(相模と金井を除く)から、猛抗議の視線を受けた絢子は、キッと睨み返した。
「なんか文句あるの!? いつもいつも私と紫ちゃんが作るドリンク飲んでるじゃないの! 私はともかく、彼女には『いつもありがとう』って、お礼を言うのが筋なんじゃないの!? それをこう言う機会で一発で解消してやるって言うんだから、ありがたく思いなさいよね! それに、7人で出せば大した金額じゃないじゃない! 男がケチケチすんじゃないわよ!」
乱暴な論理だが、口答えをしたら明日のドリンクにタバスコくらいは入れそうな絢子だから、誰も何も言えない。
やれやれ、と溜め息をついた氷室は、未だ意見を言っていない寡黙な副部長に視線をくれた。絢子が一人、熱く怒鳴っていても彼だけは涼しい顔をして、成り行きを眺めていた。ある意味、大物である。
「相模、お前は?」
「モ○バーガー」
**********
と言う訳で、バスケ部レギュラー+マネご一行がやって来たのは、学園の最寄駅前にあるモ○バーガーだった。
鶴の一声、と言えば聞こえはいいが、要は面倒臭くなった氷室と松永が相模に賛同し、その上、消極的ながらも紫ちゃんが小さく「モ○でしたら・・・」と答えたのが決定的となったのだ。
あれほど安いマッ○にこだわっていた絢子も、手の平を返したように相模に従った。何より、紫ちゃんの好きな物、と言うのが彼女を動かしたようだ。自身も女でありながら、可愛い女の子が好き、という絢子ならではである。
平均身長180センチの集団は、嫌でも人目を引く。女の絢子でさえ167センチあるのだ。162センチの金井や160センチに満たない紫は、完全に埋没してしまっている。
ハンバーガーやホットドッグに、サイドメニューや飲み物を組み合わせてそれぞれに会計を済ませ、男は各々自腹、紫には約束通りレギュラーが割り勘した。一人百円程度で済むなら、安いものである。
そして絢子はと言えば、せせこましく安くあがるようにメニューを考えていたところ、飲み物の乗ったトレイを持った相模が、ボソッと上から声を掛けた。
「結城、俺と氷室で出してやるから、好きなの頼めよ」
「へ?」
「な!」
「何でいきなりそうなるのさね!」
「何でいきなりそうなるんだよ!」
幼馴染ゆえか、見事に大声でハモった氷室と絢子に、衆目が集まる。当人たちがそれに気付いて、やや恥ずかしげに顔を背けるが、言った相模はどこ吹く風だ。
「さっきの論理でいけば、紺野よりずっと多く働いてんだから、結城の方がよっぽど奢られていいんじゃねぇか?」
真顔で言う彼を見て、絢子は目を潤々させた。
「相模、あんたいい男だぁ〜。さすがわたっ」
途中まで言い掛けた彼女は、唐突にパシッと口を手で押さえた。
「? 何だ?」
眉を顰める相模とは対照的に、氷室は呆れ顔で溜め息をつく。どうやら彼の方は、幼馴染が口を噤んだ中身を知っているらしい。
「な、何でもない何でもない! えーっと、じゃあ、お言葉に甘えて奢られてやるか」
どこかぎこちない笑顔を見せる絢子は、実は心臓が口から飛び出そうな程に緊張していた。バックンバックンと内側から叩く胸を押さえて、くるっと相模に背中を向け、顔を真っ赤にしながら店員に注文していく。
相模からはそんな彼女の頭頂部しか見えず、首を傾げながら隣の氷室に視線を移した。トレイを片手で持ち、空いた手で絢子を指差す。
「結城は何を言い掛けたんだ?」
「さぁな、知らねぇよ」
ニヤニヤと笑うその顔は、知っていても言わないという意思表示だろう。
「斎〜670円だって」
さっきまでは『如何に500円以内におさめるか』悩みに悩んでいたはずが、奢られると分かった途端に遠慮がなくなった。氷室は苦々しい面持ちで小さく舌打ちした。
「俺が払うのかよ」
「後で半分払うから、ここは頼む」
相模からすまなそうに言われ、彼らの後ろに並んでいる客が、ちょっと迷惑そうな顔をしたのを目にして、氷室は「分かったよ」と言ってトレイを相模に渡し、鞄から財布を出した。