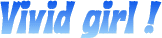思いも寄らない出来事で、バスケ部の2年生マネージャー紺野紫が、先輩である絢子に想い人を知られてしまったその日。
幸か不幸か、帰り道でその想い人である原田と、二人きりになってしまった。
この一年間、部活後は皆で帰ることが日課になっている。彼女の自宅の方角には、原田の他に桂木もいるのだが、今日に限って「家の用事があるから」と、途中下車してしまったのだ。
実のところ、紺野は登下校時に原田と二人きりになった経験がなかった。まさかこんなことになろうとは全く予想外のことで、心の準備が出来ていなかった。
夕方のラッシュに掛かるこの時間帯。紺野は、混み合う車内で自分の横に立つ原田の存在が、いつも以上に気になってしまっていた。
次第に、足の踏み場もない程に人で埋め尽くされていく車内。
彼女の隣や後ろにいる、会社帰りらしきサラリーマンやOLが、体を動かせなくなる程引っ付いてくる。別に彼女だけにくっついている訳ではないが、背丈が 150センチそこそこしかない紺野には、人の波に溺れるような感覚だ。
特に右隣にいる40代くらいのスーツを着た男が、電車が揺れる度にわざと紺野に体をくっつけてくるように感じる。やだ、この人……そう思っていた彼女の体が、突然左側に引っ張られた。
「きゃっ」
とっさに小さな悲鳴が口をつく。すると、彼女の右側に僅かな隙間が出来て、不快さがなくなった。左肩に掛かっている手が原田のものだと、紺野はすぐに気付いた。
「大丈夫か? 紺野」
首を折り曲げるようにして、原田が小さく声を掛けてくれた。チラッと彼の視線が、紺野の右隣にいた中年男に流れる。決してキツい視線ではなかったが、男はばつが悪そうに顔を背けて、わざとらしく咳払いをした。
目立つことが苦手な紺野は、咄嗟に下を向いた。痴漢とまではいかない男の行為に、原田が何か言ったらどうすればいいのか。内心オロオロしていた紺野だが、彼は睨んだだけで何もせず、ホッと胸を撫で下ろした。
自分の右半身が原田の体に引っ付くような形になっている。制服を着ていると細く見える彼だが、紺野の肩や腕、そして背中に感じるのは部活で鍛えた筋肉質の肉体。
部活でTシャツ姿の彼を見慣れているとはいえ、これほど密着したのは初めてだった。否、男子と密着するのも初めてなのだ! 紺野は心臓が飛び出しそうな程バクバクしているのを、原田に悟らないよう必死に抑え込んでいた。
原田の手は、なかなか紺野の左肩から離れていない。それは嬉しいと思うが、何故まだ離さないのか不思議だ。鞄を持つ手が汗ばみ、心臓は相変わらず胸から飛び出しそうで、紺野は喘ぐように呼吸をしている。絶対、原田から不審に思われているだろう。紺野は泣きたい気分になった。
やっと降りる駅が近付いた。紺野がホッと息を吐いた時、ホームに入った電車のブレーキが掛かって車内が大きく揺れた。油断していた紺野は大きくバランスを崩し、原田に思いっ切り寄り掛かってしまった。慌てて離れようとしたが、何故か彼の腕が腹の辺りを押さえていて、ビクともしない。
「は、原田先輩?」
「このすし詰め状態じゃ、抜けるの大変だろ。このまま降ろしてやるから、じっとしてろ」
「はい?」
この先輩は何を言っているのか? 訳が分からず紺野が固まっていることをいいことに、原田は彼女を抱えるようにして、下車する人波に紛れるようにして電車を降りた。
紺野の足は完全に宙に浮いていて、そのお陰でいつもよりスムーズに降りられた。確かに紺野の身長では、ラッシュ時は乗り降りするのに苦労している。が、何故この先輩はこんなことをしてくれるんだろう? それも、今まで散々一緒に帰っていながら、今日が初めてのことなのだ。
う、嬉しいけど……。
紺野の呟きはあまりにも小さく、彼に聞こえることはなかったようだが、顔が耳まで真っ赤なのは隠しようがない。彼女よりも遙かに背の高い原田は、とっくにそれに気付いていた。だが、彼は何も言わず、人の波から外れた場所に紺野を降ろした。
何故、こんなことになっているんだろう?
駅から自宅までの住宅街を歩きながら、紺野は前を歩く原田を上目遣いで見た。
駅のホームに降ろされた紺野は、彼に顔を見られないよう俯きながら礼を言った。そこで別れようと思っていたのだが、原田は「遅くなったから家まで送る」と言って今こうして二人で歩いているところである。
確かに、部活後にモ○・バーガーに寄ったので、いつもよりも帰り時間は遅い。そして、いつもは桂木が同じ駅で降りて、彼女と同じ方向へ帰っていく。今日はその桂木がいないから一人ではあるが、そんなに心配されるほど長い距離を歩く訳ではない。
そもそも、原田が降りる駅は一つ先のはずだ。この先輩の意図が読めず、紺野は困惑気味に彼の後ろを歩いている。
ずっと、こんなシチュエーションがあればいいと、考えたことはあった。しかし、こんな唐突に訪れるとは、心の準備くらいさせてほしいと思う。
悶々としながら歩いていた紺野は、原田が止まったことに気付かず、ボスッと彼の背中に頭突きしてしまった。
「は、原田先輩!?」
「紺野の家、ここだろ」
ハッと横を見れば、確かに彼女の自宅だ。
「あ……先輩、覚えていてくれたんですか?」
「一度通った道は、大抵覚えているからな」
ちょっとぶっきらぼうな口調だが、声は優しい。この声を聞くのも、彼女は好きなのだ。
去年の秋頃、部活中に具合が悪くなってしまった紺野を、原田が送ってくれたことがあった。後日、それが氷室部長の命令だったと知ったが、それでも紺野は嬉しかった。部員の中では比較的家が近いとはいえ、原田は一駅分を歩くことになったのだ。なのに嫌な顔もせずに送ってくれた。
それがきっかけで原田が気になるようになり、それがいつしか恋心に変わったのだ。
「じゃ、また明日な」
そう声を掛けて、原田は踵を返した。
「あ、ありがとうございました」
ペコッと頭を下げてから、去って行く原田の背中を切なそうに眺めていた紺野は、一瞬の逡巡の後、その背中を追い掛けた。
少しだけ付き合ってほしい。帰る原田に思い切って声を掛け、紺野が彼を連れてきた場所は、近くの公園だった。彼女の家から歩いて5分ほどのところにある、住宅街にしては結構な広さがある。
紺野と原田は、公園全体が見渡せるベンチに並んで座った。
少し薄暗くなった空を、鳥が群れを成して飛んでいく。
「もう暗くなるぞ。帰った方がいいんじゃないか?」
そんな彼の言葉を受け、空を眺めていた顔をうつむき加減に下げた。膝の上に置いた鞄を両手でしきりに弄り、モジモジと落ち着きがなくなった。
「紺野?」
「あの……原田先輩」
「うん?」
「…………」
喉まで出掛かった言葉が、なかなか上手く出せない。時間ばかりが過ぎていくのが、紺野にはもどかしかった。いつまでも原田を待たせるのも嫌だ。
紺野は意を決した。
「あたし……原田先輩が好きです! つ、付き合って下さい」
思い切って告白したつもりだったが、口から出た言葉は泣きたいほど小さな声だった。鞄の上で両手は拳を握り、体は強張っている。とても原田を見ることが出来ず、目はキュッと瞑っていた。
「いいよ」
暗闇に響く原田の声。あまりに短い答えに聞き間違いかと思い、紺野はオズオズと顔を上げた。
「え?」
「人から好きだって言われるのは、結構嬉しいもんだな」
「せんぱい?」
ぼんやりと見上げる原田は、少し照れているような表情をしていた。その顔が次第に歪んでいく。自分の目に涙が溜まっていることに、紺野は気付いた。
「ほ、本当ですか?」
「うん、紺野は可愛いし。俺でよければ」
「あ……ありがとうございます」
呟いた言葉は消えるようにか細かったが、万感のこもった声は原田にしっかりと届いていた。