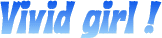相模が部屋に戻ってくると、結城がベッドに座っていた。
「はあ……」
ガックリ肩を落として、盛大に溜め息をついている。
「そんなに俺と同室は嫌なのか?」
「うひゃ!?」
ビョンッと飛び上がった結城は、慌てて振り返った。
「さ、相模! おどかさないでよ!」
「氷室に言えば、変えられるんじゃないか?」
「でも……」
結城はむくれた顔でうつむいた。彼と同室が嫌なのではない。むしろ歓迎ではあるが、いきなりこんなことをされて、気が動転したのだ。高校生の身で男女同室というのも、如何なものかと思ってしまう。学園にバレたら部活停止になってしまうかもしれない。
悪い展開が頭を巡り、素直に喜べないのもあった。
「相模は? 私と同室で嫌じゃないの?」
「ああ、俺はいいけど。結城が嫌なら、俺が氷室の部屋に移動しようか?」
「え!? でも……」
「結城次第だよ。どうする?」
首を傾げながら問われて、結城は答えに窮した。
「部活のこととか考えずに、結城自身がどうしたいか、考えろよ」
ポンポンと彼の手が頭を撫でていき、相模はタオルと着替えを持ってバスルームに入っていった。
「あ、先にいいか?」
一度入ってから顔を出して訊いてくるところは、実に彼らしい。結城は心ここにあらず、といった表情でうなずいた。
程なくしてドア越しにシャワーの音がかすかに聞こえてきた。ふうっと溜め息をもらす。
相模と同室は嫌じゃない。気持ちの上では小躍りしたい気分だ。多分氷室なら、絶対に学園にはバレないような対策をしているだろう。それなのに素直に喜べないのは、相模の真意が読めないからだった。
彼女と同室になったというのに、大して動揺も見せず、嬉しそうな様子もない。
氷室には恋人らしくないと思われているが、相模とは何度かデートらしきものもしたし、二人で出掛けた時は、手だって繋いでいる。そんな時、自分は柄にもなくドキドキしているというのに、彼はちっともそんな風に見えないのだ。
晴れて付き合い始めて早1ヶ月。彼は自分のことをどう思っているのか。付き合ってみないと分からないと言っていたが、それで彼の気持ちに変化はあったのだろうか?
一緒にいても、相模が何を考えているのか、その表情からは全く読むことが出来なかった。正に鉄壁のポーカーフェイスだ。
結城が悶々としている間に、シャワーを終えた相模が出てきた。Tシャツにスウェット姿だ。濡れた髪をタオルで拭きながら、結城と向かい合うようにベッドに腰掛ける。
部活で鍛えた筋肉質の肉体がシャツ越しに見て取れ、襟元から覗く鎖骨に視線が行ってしまい、結城は頬を赤らめて目をそらした。
「結論は出たか?」
「うん……ねぇ、付き合う前に相模は言ってたじゃん。私に恋してはいないけど、付き合ったら変わるかもしれないって」
それは相模にとって予想外の言葉だったようで、しばし目を見張り、やがて溜め息のように息を吐いた。
「急にどうしたんだ?」
「だって、相模の気持ちが分かんないだもん。私と同室は構わないって言ってても、ちっとも嬉しそうじゃないし。簡単に斎の部屋に移るって言うし」
「結城は?」
「え、私?」
逆に問われて、結城は目を丸くした。
「結城は、俺のことをどう思っているんだ?」
「どうって、好きだよ。今だって、凄くドキドキしてる。なのに、相模は何にも変わらないんだもん」
少なくとも結城の目には……というより、誰が見てもそう感じるだろう。
口を尖らせて不満な様子をアピールする結城から目を逸らし、相模は大きく息を吐いた。髪の毛を拭いていたタオルは、そのまま頭から被っているため、表情はよく見えない。
「結城はさ、部活をしている俺を見てどう思っていた?」
「どうって、どういうこと?」
「楽しそうとか、悔しそうとか」
「えっと……あんまり」
好きだと自覚する前からの相模の部活での様子を思い出し、結城は遠慮がちに答えた。言われてみれば、彼はあまりそういうことが表情に出ていなかったように思う。氷室でさえ、バスケが好きだという想いが体から滲み出ていたものだ。
相模はそんな答えに気を悪くした様子も見せず、頭に被っていたタオルを外して、さっきと同じ様に息をついた。
「俺ってさ、あまり顔に出ないんだよ。気持ちとか、そういうの」
「うん。それは今思い返して、そう思った」
遠慮のない彼女の言葉に、タオルの陰で苦笑をもらした。それはポーカーフェイスの相模には珍しく、気持ちがストレートに出ていた瞬間だった。残念ながら、結城にそれが見えることはなかったが。
「だから分かりづらいかもしれないけど、俺は俺で結構心の中は乱れまくっているよ」
「ホントに?」
「ホントに」
そうは言われても、そう平然とした顔を向けられては、結城には信じがたい。感情が豊富に表に出るのが常な彼女には、理解の範疇ではなかった。
「じゃあ、どのくらい乱れまくっているのか、言葉にしてみてよ」
「今?」
「そ、今の」
相模は、どこか困ったような顔で首を傾げ、それから目を伏せて口を開いた。
「夜、結城を襲いたくなったらどうしよう、とか」
「ええ!? それはないでしょ」
相模に限ってそんなことはないと、本気で思っている結城は、思わず笑い飛ばしていた。そんな彼女の様子を無言で眺めていた相模は、僅かに眉を寄せて首を傾げた。
「なんでそう言い切れるんだ?」
「だって、相模だよ? 二人きりで手を繋いだって、平静な顔してるじゃない」
「そうでもないよ、結構ドキドキしてる。結城の手、柔らかくて強く握ったら壊れちゃいそうだし」
「え……」
それは思い掛けない言葉で、結城は中途半端に固まった。
「頬もマシュマロみたいにぷにぷにしているし」
「へ?」
以前に頬を触られたことがあるのを思い出し、結城の顔は真っ赤に染まる。あの時は、相模が何故そういう行動を起こしたのか分からなかった。見た目はいつもの彼だったのだ。今、目の前で信じられないことを言う彼もまた、いつものポーカーフェイスである。
「ちょ、ちょっと何言ってんの? 相模」
「結城が言えっていうから、俺が結城に対して思っていることを言ってるだけだよ」
「だ、だからって」
「意外?」
「そりゃもう。相模じゃないみたい」
顔を真っ赤にしていても、結城は結城である。相変わらず遠慮がない。相模は苦笑するしかなかった。
「俺って、そんなに感情がないように思われてたんだ」
「だって……本当にそうだったら、ちゃんと顔に出してよ。そんな苦笑いばっかりじゃなくてさ」
口を尖らせて拗ねる結城を見て、相模は再び困ったように首を傾げた。
「どうしたら感情を表に出せるのか、よく分からないんだ」
「相模って、怒ることないの?」
「そりゃあるよ。ただ、感情的に声を上げたり、それをむき出しにしないだけ。ああ、でも結城に告白された時は、呼び出した氷室と睨み合ったことがあったな」
あの時は、冷たい感情が腹の辺りに落ちていくような感覚があった。決して声を荒げることはなく、怒っていても他人からはそうは見られないことは、よくあることだ。普段からそう自己分析をしている相模であったが、それを言葉にすることはない。
高城や桂木のように、嬉しくてはしゃぐということもない。氷室の感情表現は相模に近いものはあるが、それでもよく表に出ているものだ。どうすれば、そのように気持ちを外に出すことが出来るのか、相模には分からないでいる。
「じゃあ、訊くけど。あたしのこと、好きになった?」
恋人の言葉に、結城はどうしても確信が持てないらしい。あまりにもストレートな問いに、相模はじっと彼女を見つめ、それから困惑したような表情で話した。
「恋愛感情かどうかの判断は分からないけど、結城のことは好きだと思う。こういう状況になって、もしかして結城を襲いたくなることがあるんだろうかって。そうなったら、自分がどうなるのか分からなくて怖いとは思うよ」
「何だかその言い方って、心理分析みたい」
「外れてはいないだろうな。でも、感情ってそういうものだろ?」
「そうなの? あたしは何だか素っ気無く感じる。本当にあたしのこと好きって思ってる?」
不安げな様子でしつこく訊いてくる結城を、相模は邪険にすることはなかった。
「好きじゃなかったら、普通は同じ部屋って嫌じゃないか?」
「嫌じゃないの?」
「さっきそう言ったろ。意外ではあったけど、嫌じゃないよ。結城がいいなら、俺はここでいい」
僅かであったが微笑を浮かべて言う相模を見て、結城は再び顔を赤らめた。ポーカーフェイスでいても彼の顔立ちは柔和なため、微笑むと更に優しげになるのだ。
相模がそういう表情を見せるのは、自分の前だけだということを、結城はまだ気付かずにいた。