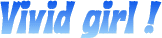会議室に移り、勉強を始めて30分ほど経った頃、結城がソワソワし始めた。
実は彼女はそれほど成績がいい方ではない。幼馴染と比べて、ではあるが、大抵は中の上辺りをウロウロしている。特に語学が苦手で、さっそく英語の宿題につまずいていた。
ウンウン唸っても、辞書をめくっても、分からないものは分からない。
チラッと相模の方を見ると、部活のファイルを見ながら、氷室と小声で何か話している。
彼は卒業後にアメリカの大学に留学するため、この6月にSATや TOEFLを受けていた。自分の分からない英語の問題なんて、彼にしてみればチョー簡単に解いてしまうだろう。
そうなることを期待しているのだが、素直に訊きに行くことが出来ない。これだけ他人の目があると、彼女の性格ではとても素直な行動は取れなかった。だが、視線だけはどうしても彼を見てしまう。
幼馴染みの視線に気付き、且つその意味を理解した氷室は、相模とのミーティングを早々に打ち切った。未だ話の途中、怪訝な表情の相模に、氷室はさりげなく結城の存在を示した。
想い人の視線がこちらに向き、結城は慌ててノートを見た。静かな会議室に椅子から立ち上がる音がする。必死に問題を解いている振りをしていた彼女は、空いていた隣の席に誰かが座る気配に気付いて顔を上げた。
「さがっ」
思わず大きく声に出してしまい、慌てて口を押さえる。そして相模の方に体を寄せ、声を潜めた。
「なんで? 斎と打ち合わせしてたんじゃないの?」
「その氷室に言われて来たんだ。どうした?」
「ど、どうしたって……」
予想外の展開に、結城はゴニョゴニョ言い淀んだ。相変わらず自分の前では引っ込み思案の彼女に微笑みを浮かべ、相模は開いたままのノートを見た。
英文の穴埋め問題だ。動詞を入れる場所は埋まっているが、それ以外が抜けたままになっている。
「結城」
「な、なんじゃい?」
唐突に呼ばれてちょっと椅子から飛び上がり、結城は赤い顔上げた。そんな突飛な行動にも驚くことなく、相模は悠然とノートに指差した。
「ここは前置詞を入れればいい」
「ぜんちし?」
「asとかofとか aboutとか、そういう類いの単語」
「それが一番分かりづらいのよ!」
「パターンを覚えれば簡単だって」
相模は一つ一つ丁寧に教えてくれた。結城は聞き漏らすまいと、一生懸命耳をダンボにしていたが、元々苦手な科目も手伝って、半分は頭の中を通り過ぎていた。
「……というわけ。分かっただろ?」
「うう……まぁ、何となく」
「とりあえず解いてみな」
言われてとりあえず空いていた部分を埋めていったが、自信などこれっぽっちもなかった。
「こんな感じ?」
「ふむ、正解率8割ってところだな」
「え…… ほ、ホントに?」
好きな相手に誉められて嬉しくない訳はないが、自信がないために疑い深くなっている。そんな彼女を見て、相模はおかしそうに笑った。
「結城は頭がいいんだから、苦手意識を克服すれば、すぐに分かるようになるさ」
「頭、いい……かな?」
「いいと思うぜ」
恋人に誉められて悪い気はしない。結城は見つめられることに我慢出来なくなり、また下を向いた。会議室にいる部員たちから視線を向けられているのが分かる。
この視線をどうしたもんかと考えている結城の前に、ノートを破いた一枚の紙が差し出された。
「なにこれ?」
「よく使う前置詞のパターンを書いた。これを暗記すれば、大抵の英文は問題ないだろ」
「え、今書いたの?」
「? ああ」
この短時間で、結城にとっては信じられない神業を行なった相模は、下からの不審そうな視線に怪訝な表情で答えた。ほんの数分で20個近い例文を作れる彼の英語力の高さに舌を巻くと共に、さり気なくこういうことが出来るのが彼らしいと感じていた。
そういうところに自分は惚れたのだと、今更のように気付いたのだった。
お勉強タイムを終えて、バスケ部員たちはそれぞれの宿泊部屋へと引き上げた。
そのまま夕食の時間に突入する。何と言っても運動部だ。特にバスケは運動量が半端なく多い。そのため、部員は常に腹っぺらしである。我先にとラウンジに駆け込み、食事にあり付いていた。それはレギュラー陣も同じである。
体育館と会議室の施錠を済ませた結城は、部員たちより遅れてラウンジに入る。空腹に耐え兼ねて、部屋には寄らずに荷物を持ったままである。
そんな結城の姿を見付けた氷室が手招きで呼び寄せる。勿論、相模と相席にするためである。部長副部長コンビのテーブルには、トレーに乗った夕食の献立が準備されている。ちなみに氷室の主菜はハンバーグステーキで、相模のはカツ丼である。
結城はふらふらと幼馴染の元へと行き、重たそうにバッグを床に無造作に置いた。
「ああ、お腹空いた。これ、取りに行かなきゃいけないんだよね?」
ラウンジの食事はセルフサービスなのだ。いくつかのメニューが日替わりで用意されており、好きなだけ食べることが出来る。
結城は随分と疲れているようで、席に着くとテーブルの上に突っ伏した。腹は減っているが、取りに行くのは億劫である。
氷室はそんな彼女を尻目にとっとと食事を始め、相模は黙って結城のために食事を取りに席を立った。
「結城、何を食べる?」
「あったらオムライス。なかったら、何でもいいからガッツリ系」
無慈悲に食事をしている幼馴染を、突っ伏した腕の間から恨みがましく睨んだ。
「斎、鬼。相模を見習いなよ」
「あいつが取りに行ったんだから、俺はいいだろ」
「女の子がお腹空かせているのに、その目の前で食べるっていう行為が鬼だって言ってんの」
「女の子ぉ? 誰が?」
鼻で笑われ、結城は顔を上げて幼馴染を睨みつけながら、自分を指差した。
「恋心を持て余してる、かわい〜い女の子」
「持て余してるってのは認めるぜ。お前ら、ちっともカレカノっぽくねぇもんな」
「私だって気にしてるわい! だってさぁ、相模って全然感情が読めないんだもん」
「だよな。俺もたまに迷う時がある」
結城の目には、しょっちゅう意思疎通をしているように見えるため、驚きの表情でもって氷室を眺めた。
「迷うって?」
「あんまりにも自然に振舞うんで、怒ってると分からなかったりしたことはある。それ以来、こいつは怒ってんのか、そうじゃねぇのか分からねぇ時がある」
「そういうことあったんだ?」
「ストリートの大会でな」
その時、結城の前に湯気の立つオムライスの乗ったトレーが差し出された。
「結城、これでいいか?」
「うん、ありがとう、相模」
恋する乙女とはいえ、まだまだ花より団子なお年頃。結城は、話は後に置いておいてオムライスを頬張り始めた。
向かいの席では、相模がカツ丼を食べている。高城や原田など、他の部員たちはがっつくように食べるが、相模と氷室はいつも静かに食べる。がっつく姿など、部員はおろか結城でさえ見たことはなかった。
食事を終え、それぞれに食器をカウンターに片付けに行く。バスケ部の半分以上は部屋に引き上げ、他の運動部の部員たちも殆どラウンジを引き払ったらしく、さっきまで賑わっていたフロアは閑散としていた。
「俺は先に部屋に戻る」
そう言って相模も引き上げてしまった。恋人が目の前にいるというのに、随分と淡白な態度だ。結城も、何となく不満気である。
「そんなに相模の気持ちが気になるなら、ズバッと訊いちまえよ。絢子らしくねぇ」
「そんなこと出来るわけないじゃん。相模に嫌われたくないもん」
「別に怒りゃしねぇだろ。第一、表に出さねぇあいつが悪いんだ」
食事後のコーヒーを飲みながら、氷室が他人事のようにのたまう。結城の前には、紅茶のカップがある。
ラウンジには、いつでも自由に飲めるドリンクバーがあるのだ。フロアの隅のテーブルで、勉強している学生もまばらにいた。
「私だって努力してるつもりなのに、相模って素っ気無いんだよね」
「溜め息ついてたって、しょうがねぇだろ。もう一歩踏み込んでみりゃいいじゃねぇか」
「もう一歩って?」
「名前を呼び合うとか」
氷室に促され、ボソッと相模の名前を呟いた結城は、いきなり顔を真っ赤に染めた。ボンッと音がしたかのように唐突で、湯気まで立っている。言いだしっぺの氷室は、それを見てギョッとしていた。
「お前、恋人ならそれくらい当然だろ」
「だって、だって、あ、あ、暁生って呼ぶの?」
「俺のことは斎って呼び捨てじゃねぇか」
「一緒に出来るわけないでしょ!」
しかも、相模からは「絢子」と呼ばれるのだ。それを想像した瞬間、結城の顔がヘラッと締まりのない表情になる。
「絢子、気味悪ぃぜ」
「だって、相模から絢子って呼ばれたら……」
呼ばれたら、呼ばれたら……。
結城の心の中で、自分の言葉がエコーで広がる。そんなことにでもなったら、心臓が止まってしまうかもしれない。
酸欠状態のような呼吸で、何とかそれを伝えると、幼馴染は心底おかしそうに笑った。
「そんなことにでもなったら、相模に人工呼吸でもしてもらえよ」
「ぎゃーっ、やめて、やめてよ、そんなこと言うの!」
居た堪れなくなった結城は、いきなり席を立つと、自分のバッグを持って逃げるようにラウンジを出て行った。
その姿を呆然と見送った氷室は、くつくつと笑いながら残っていたコーヒーを飲み干した。そして、残された結城のカップと共に、自分のそれを片付けるために席を立った。