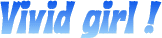関東大会も優勝で締めくくり、昨年は準優勝に泣いた全国大会には優勝で飾ろうと、氷室以下冬泉学園高等部バスケ部は、燃えに燃えていた。
夏休みに入り、強化合宿にやってきたのだ。
場所は山中湖畔にある、学園所有のスポーツ部専用の合宿所。さすがに金持ち校の合宿所だけあって、全館冷暖房完備、男女それぞれ大浴場があり、各部屋二人様の洋室にはシャワーもついている。
食事も掃除も館内のスタッフが行い、生徒と顧問の教師は部活にだけ集中出来るのだ。また、それぞれの部に必要なコートや道具も一通り揃えられ、バスケ部も体育館を丸ごと一つ使える贅沢さ。
至れり尽くせりなサービスは、リゾートホテル並みだ。
更に、成績の良い部はいつでも無料で使えるが、成績不振な部は申請して許可が降りない限り使用出来ず、更に利用料金も発生するという厳しい掟がある。利用料金といっても、相手は学生なので、せいぜい一日ワンコイン程度だが。
もちろんバスケ部は、無料で使い放題である。
氷室と相模、部長副部長の打ち合わせで、この夏休みは全国大会までこの合宿所に滞在し、みっちり練習することに決まった。
都大会優勝後に晴れて付き合うことになった副部長の相模とチーフマネージャーの結城だが、これまで恋人らしい二人の姿は見受けられない。精々、相模にドリンクやタオルを渡すのが、確実に結城の担当になっていることくらいだ。
結城の幼馴染みである氷室でさえ、本当に付き合っているのか確かめたくなるほど普通なので、他の部員やレギュラーたちは付き合っている事実も知らないでいる。
合宿所に着くと、早速部活動を始めたバスケ部の面々。アップを終えたレギュラー陣に、合宿中のメニューを書いたボードを持った結城が近付いてきた。
「はいはい、レギュラー陣注目! 今回の合宿では、体力面とフォーメーションを強化するよ」
事前に氷室、相模と打ち合わせたことだ。レギュラーたちもそれは知っているので、ゲッという表情をしながらも、口答えはしない。
「何たってウチは去年準優勝したんだから、初戦敗退なんて恥ずかしい真似晒したら、ただじゃおかないからね!」
部内では誰よりもおっかない結城の言葉だ。誰も逆らおうとは思わない。
「もし初戦敗退なんて恥さらしをやらかしたら、全員笑い殺しの刑に処す! 心して特訓に励むように!」
笑い殺しの刑って何だ? と、この場にいる誰もが思ったが、口に出しはしなかった。何はともあれ、勝てばいいのだ。結城の指示でそれぞれ渡されたメニューに従って、適当にバラけていく。
レギュラー以外の平部員たちも、結城が作った特訓メニューに従って、既に活動を始めていた。
「紫ちゃん」
結城が次に呼んだのは、部内で彼女以外には唯一人のマネージャーだ。マネージャーとなって2年目。結城によって鍛えられ、今では「紫ちゃんあれ」で通じるほどになった。
その紺野紫は、休憩時間に間に合わせるように、タオルとドリンクを用意しているところだった。
「はい、結城先輩、何でしょう?」
作業を中断し、結城の元に駆け寄る。彼女はここ1ヶ月で目覚ましく成長した。何があったのか知らないが、内気だった性格が僅かだが、積極的になってきたように結城は感じていた。
いい傾向だと彼女は喜んでいる。全国大会が終わったら、結城たち3年は引退する。これからのバスケ部を引っ張っていくのは、彼女たち2年生なのだ。当人たちには知らせていないが、この合宿は彼ら2年部員たちの精神的な成長を促す目的もあった。
「この合宿中、平部員の面倒は全部紫ちゃんに任せるから、よろしくね」
「はい……えっ!? 結城先輩は!?」
「私ゃレギュラー連中を見るから」
「え、で、でもあたし何をやればいいのか……」
突然仰せつかった大役に、紺野は目を白黒させている。
「いつも通りのことをやってればいいんだから、大丈夫だよ。分からないことは遠慮なく訊いていいからさ。紫ちゃんならやれるって信じてるから、心配してないよ」
そう言ってパチッと片目を閉じ、次の仕事へと向かう。残された紺野は、青ざめた顔でムンクの叫びのようになっていた。
昼休み。
合宿所には専用のラウンジがあるが、昼食は結城の方針でおにぎり好きなだけとおかず一品である。
ここの厨房のオバチャンたちに直接交渉して、バスケ部だけ昼食におにぎりを作ってもらうことに成功したのだ。ラウンジに出掛けてしまうと、午前中に作れたいい練習のリズムが壊れてしまうことがある。効率よく練習するための労力を、結城は惜しまなかった。
昼食に結城がおにぎりを出してくれたことに、レギュラー平部員共にいたく感動した。明らかに、結城が作ったと勘違いをしているが、もちろん本当のことなど教えない。勝手に勘違いして勝手に頑張ってくれるのだから、彼女にしてみれば一石二鳥なものだった。
一時間の昼休みを挟んで、午後は4時までみっちり練習し、その後は夕食まで勉強である。
「げっ、合宿に来ても勉強すんのか!?」
部活が終わり、やっと解放されると喜んでいた桂木と高城は、部長からのお達しに猛抗議をした。しかし、氷室は全くひるまなかった。
「自由時間にしたらお前ら、ゲームばっかりするだろ。夏休みの宿題くらいやれ! つか、お前ら今年受験生って自覚を持てよ!」
図星を指され、更に痛いところを突かれても、高城は抗議を諦めなかった。
「煩いよ高城! あんたたちが成績不振で卒業出来なかったら、全国大会まで合宿するって決めた斎と相模が責任取ることになるんだからね!」
これまでは結城に言われるとスゴスゴと引き下がっていた高城だったが、今はもうフラれた身。意外にしつこかった。そこに口を挟んだのは、副部長の相模である。
「高城、宿題なら全員でやれば楽に終わらせられるだろ。せっかくみんなといるんだ、家に帰ってから一人でやるより、ずっと効率はいいぜ」
相模の冷静な言葉は絶大な説得力があった。これには、高城もケチをつけることは出来ず、部活後の体育館で学年ごとに車座になり、夏休みの宿題をすることになった。
部活中は甘やかしはいけないと、クーラーを切っていたが、勉強となれば話は別。結城が冷房のスイッチを入れたお陰で、全員快適に宿題をすることが出来た。
ちなみに彼らは、エスカレーター式で冬泉の大学に行く者たちである。
彼らとは別に、外部の大学を受ける者は、そんな生易しい勉強ではとても追い付けない。
そこで結城は合宿中にバスケ部が使える会議室を確保し、ガッツリ勉強したい連中の要望にも応えたのだった。
会議室を使うのは、部長副部長と原田に金井、結城と紺野のマネージャーと一部の二年生平部員である。