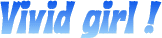第3クォーター終了後の2分間のインターバルに、絢子はタオルとドリンクを持って、相模の元に寄っていった。
「さっきの話だけどさ」
「うん?」
「相模のプレー見てたら、ちゃんと話そうって思ったんだ。だから、いいよ」
きっぱりと自分を見上げて話す絢子に、相模はふっと相好を崩した。
「ありがとう結城」
そう言って絢子の頭をポンポンと撫で、その手で彼女の前髪をかき揚げた。初めてされる相模からの、何やら意味深な行動に、絢子は耳まで顔を真っ赤にして、彼を見上げている。心臓が肋骨を突き破ってしまいそうな程バクバクしていて、呼吸もままならない状態だ。
「う…あっ…あの、さ、相模。これ…なんの意味が?」
「別に。ただ、結城の瞳めが見たかったんだ」
真剣な表情で答える相模。絢子は緊張し過ぎて、ゴクッと生唾を飲み込む。
「な、な、なんで!?」
「いつも前を見ているし、たとえ迷っても必ず前に進むだろ。だから、見たかった」
「? どういうこと?」
訳が分からない絢子に、相模は優しく笑い掛けた。
「後で話すよ」
そう言って、タオルとドリンクを彼女に渡し、コートへと踵を返す。とっさに彼の左腕を掴んだ絢子は、その体が異常に熱いことに気付いた。
「ちょっ…凄い熱じゃないの!」
立ち止まった相模が振り向き、口の前で右手の人差し指を立てた。
「黙ってろって……せめて斎にだけは言っといた方が、いいんじゃないの?」
「大丈夫だ。あと10分、何とか持たせるよ」
「わ…笑いながら言うことじゃないでしょ!」
彼の鈍感は、自分の体にも及ぶのか。絢子は呆れて怒ったが、内心はハラハラしていた。明らかに、先月自分が寝込んだ時よりも、彼の体は熱かったのだ。
だが、相模は第4クォーター開始の合図を聞いて、コートへと駆け出していく。
「マジで!? あんなんじゃ、試合中にぶっ倒れちゃうんじゃないの?」
心配している絢子をよそに、試合は第4クォーターが始まった。休んでいた松永と金井がコートに入り、代わって桂木と高城が残った。
「た、高城!? なんであんたがいるのよ!?」
「俺だって知るか! 相模に追い出されたんだよ!」
憤然と言い返す高城は、タオルを首に巻いて汗を拭いている。チーム中一番ノッポの彼がいないのは、この終盤かなりキツイはずなのだが……。
「何か知らねぇけど、体休めとけって言われた」
「ああ、なるほど。後で交代するってことじゃない? 言われたからには、ちゃんと休んでおきなさいよ」
「言われなくたって、分かってら!」
怒鳴りながらもベンチに座る高城。絢子は、腕を組んでコートを見た。
ポイントガードとして指示を出しながらプレーしている相模は、傍目にはいつも通りに見える。否、試合開始から殆ど変わってはいないのだ。一体いつから、あんなに高い熱を出してプレーしていたのか。
「全く……全然気付かなかったなんて、マネージャーの名が廃るわよ!」
呟くような声だったが、思わず口に出てしまい、傍にいた紫が怪訝な表情で絢子を見上げた。
「絢子先輩?」
「んっ、何でもないよ。それより今のインターバル、紫ちゃん一人に仕事やらせちゃって、悪かったね。ごめん」
組んでいた腕を解いてちょこっと頭を下げる絢子に、紫は慌てて両手を体の前で振った。
「そ、そんなことありません! いつもは絢子先輩が、一人で動いているじゃないですか。あたしなんて、まだまだです。もっと勉強しなくちゃ!」
紫は、鼻息も荒く宣言し、絢子は嬉しそうに頼もしい後輩を見下ろした。
「あっ!!」
その紫が声をあげた。その緊迫した様子に、絢子もコートを見る。
「斎!?」
冬泉ゴールの真下で、部長の氷室がコートに腰から落ちたところだった。どうやら、シュートをした際に江南のセンターからチャージを食らい、バランスを崩して倒れたらしい。だが、彼の放ったシュートはゴールに吸い込まれていた。
氷室は痛そうに腰を撫でつつ、相模に腕を掴まれて立ち上がる。一瞬、彼の目線が自分の腕を掴む相模の手に注がれ、表情を曇らせたことを幼馴染の絢子は見逃さなかった。
「うーん……斎、分かっちゃったな」
「はい? 何をですか?」
「うんにゃ、何でもない」
相模にはああ言った絢子だが、本人が持たせると言っている以上、余計な口出しは出来ない。顔はコートに向いたまま、首を左右に振る先輩マネージャーを、紫は不思議そうに見ている。
「部長、大丈夫でしょうか?」
「斎は心配ないよ。あれで結構頑丈だし、ストリートじゃあんなのザラらしいから。それよりも紫ちゃん、スコアボードはちゃんと付けておいてね」
「はい!」
元気よく返事をする彼女の手には、ちゃんとボードとペンが握られている。抜かりの無い後輩に、絢子は満足そうに頷き、再びコートを見た。
「でもまぁ、これで斎が怒っちゃっただろうから、これから荒れるだろうねぇ、この試合」
ボソッと呟いた言葉は後輩に聞かれることはなく、絢子がふと目が合った相手はその斎だった。
「ありゃ、こりゃまた相当怒ってるねぇ」
「はい?」
「今ので斎がプッツンしちゃうかも。荒れるよ、この試合」
「…………大丈夫なんですか?」
息を呑んだらしい後輩の僅かな沈黙。
「そんなに心配する必要はないさね。荒れるって言ったって、ルールの中でのことだから。ま、見てれば分かるよ」
それより心配なのは、相模の方だけどね。熱があるのが、さっきので斎にバレただろうし……。
胸中でそう付け加え、絢子はハラハラする己の気持ちを、必死で落ち着かせた。
だが、絢子の心配をよそに、その後の試合は大して荒れることなく、無事に終わった。
スティールやチャージングや強引なカットインや、バスケットカウントを狙った(敵のファウルを誘う)シュートなど、見る者が見れば、氷室がやたらと江南選手の敵愾心を煽り、挑発して自滅させるプレーをしていたが、やり方が上手いために審判に悟られることなく、98対76で冬泉が勝利した。
最後の礼をした時、江南の選手たちから白い目で見られていた氷室だが、本人はそんなものどこ吹く風だ。
引き上げてきたレギュラーを迎えた絢子は、妙にスッキリした顔の幼馴染に近寄っていく。
「全くもう、見ていてこっちがハラハラしたよ!」
「俺がそうそうヘマをやるかよ。ま、気分は晴れた」
「そりゃそうでしょ! あれだけやりたい放題していれば」
しれっとぬかす氷室に絢子は呆れた口調で返し、次いで表情を曇らせた。
「それより、相模のこと分かっちゃったでしょ? なんで交代させなかったのよ。もし倒れたりしたら」
「本人がやるって聞かなかったんだよ。高城を最後に入れた時だって、絶対に下がらなかったからな。あいつ、意外に頑固だからな。大丈夫か?」
「平気だよ。ちゃんと相模と話をするって決めたんだから。この後で」
「へぇ! ま、頑張れよ。あんだけ熱があって、相模がまともに話出来りゃいいけどな」
言いながら彼が向けた視線の先には、部員からタオルとドリンクを受け取っている相模の姿。高城や原田と何か話をしているようだが、その様子からは高熱を発しているようには、全然見えない。
「頑固って言うのは分かるよ。去年、バスケ部やめるつもりだったって、さっき聞いたからね」
「俺が引き留めた」
「それも聞いた。何でかなんて聞く気はないけど、よく相模が承知したね。去年のうちに相模がいなくなってたら、私の今の気持ちも変わってたかもしれないよ?」
じっと相模を見つめながら話す幼馴染の言葉に、氷室は意外そうに彼女を見下ろした。
「そうなのか?」
「多分……人間て分かんないね」
どこか悟ったような表情を見せ、絢子は忙しく働く紫を手伝いに向う。一人残された氷室は、離れていく幼馴染の後ろ姿を見ながら、タオルで汗を拭きつつ溜め息をついた。
「ホント、人間て分かんねぇよな。お前が相模に惚れるなんて、俺は思ってもみなかったんだぜ」
氷室のそんな呟きは、誰に聞かれることもなく、空中に消えていった。