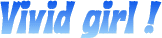うぉ〜〜!
体育館に客席からの割れんばかりの歓声が響いた。冬泉学園バスケ部の名物コンビプレーが炸裂したのだ。相模からのノールックパスを原田が中継し、氷室がアリウープを決めた。
今日は全国高校バスケ大会都大会の決勝戦。3年連続優勝を狙う冬泉と、その冬泉学園をライバルとする江南との決戦とあって、会場は大いに盛り上がっていた。
NBAばりのスーパープレーで、前半第2クォーターが終了した。15点もの点差を突き付けて、冬泉が圧倒的有利である。
ハーフタイムとなり、コートから引き上げて来るレギュラーたちを、マネージャーの絢子と紫が、タオルとドリンクを持って迎える。ベンチにいる部員たちも、キビキビと彼女たちをサポートした。
絢子が相模に告白した日から、およそ1ヶ月が経っていた。
その間、絢子にも相模にも目立った変化はなかったが、原田のような敏い人間は、絢子の微妙な態度の違いに気付いていた。それは、相模に対した時だけ、僅かだが態度がよそよそしくなるのだ。パッと見は普段通りで、殆どの人間はそんな彼女の様子に気付いていないが・・・。
一方の相模は、まるで何事もなかったかのように平静だった。氷室にも絢子にも、対する態度は変わらない。ように見える。
「絢子」
部長の氷室が、チーフマネの絢子を呼んだ。彼女は前半、一番走り回っていた松永の足を、丁寧にマッサージしているところだ。
日頃から鍛えているとはいえ、松永はレギュラー経験が最も短く、また試合というのはどんなに注意していても、普段の練習通りにはいかないものだ。
他のレギュラーたちは経験値もスキルもあるので、放っておいても自分たちで何とか出来る。
絢子は松永に何かを告げて、氷室に顔を向けた。
その一瞬、彼女の肩が微妙に揺れたのを、氷室は見逃さなかった。彼の傍らには副部長の相模がいたのだ。
二人共チームの中心として、試合中はずっと走り回っているので、相当に呼吸が激しい。氷室は、見た目ほどには疲れていないようだが、相模の方は少し苦しそうな表情で、タオルで汗を拭っていた。
どんなに厳しい試合でも、相模が表情を崩すことはあまりない。氷室はやや心配そうに彼を見たが、見られた本人は「平気だ」と言うように笑っている。
絢子は近くにいた平部員に松永を任せ、すぐにやって来た。
「何じゃい、斎」
「後半、第3クォーターは松永と金井を引っ込める。その間によく休ませといてくれ。特に松永は」
「終盤、足に来ないようによくマッサージしとけ、でしょ。私がやらない訳がないっしょ」
「ま、そうだろうな。頼りにしてるぜ」
口調は茶化したものだが、氷室の声には絢子に対する揺るぎない信頼がこもっている。
「話はそれだけ?」
彼女らしくないそわそわした聞き方なのは、相模が傍にいるからだろう。
一秒でも早くここから立ち去りたい気持ちが如実に出ているが、珍しいことに絢子自身がそんな自分の状態に気付いていなかった。
何も言わない氷室が相模に視線を移したので、絢子はこれ幸いと二人から離れようとしたのだが。
腕をガッチリ掴まれてしまった。犯人は氷室だ。
「斎?」
「じゃあな、後は二人で話せ」
「え!?」
絢子が面食らっている間に、氷室はみんなのいる方へ行ってしまう。
「え……ちょっと斎?」
「結城」
相模の静かな声に呼ばれ、絢子はギクッと体を硬直させた。
この1ヶ月、常に平常心を心掛けて来たが、あまり上手くいったことはない。返事はいいと言ったのは自分だ。だが、本心は彼が自分をどう思っているのか、とても気掛かりだったのだ。
「な、なに? 相模」
自分でも呆れてしまうほどの硬い声。絢子はどうしても相模と視線を合わすことが出来ず、そっぽを向いたままだ。が、相模は気にした風もなく話を続けた。
彼の呼吸が少し荒いことに絢子は気付いたが、それを言及出来るような状態ではなかった。
「今日、試合が終わった後で、時間あるか?」
「え? あ……まぁ、あるけど」
相変わらず絢子の口調は歯切れが悪い。相模に声を掛けて貰えて嬉しいのだが、素直に喜べないのは複雑だ。相模は絢子の返答に頷き、続けた。
「話があるんだ。二人で帰らないか?」
「!」
予想はしていたとはいえ、絢子はそう訊かれて息を飲む。
「あの時、返事はいいと言ってたが、この先もそのままって訳にはいかないだろ」
「でも相模は……」
「試験は終わった」
「う……」
逃げる口実を失って、絢子は口ごもった。