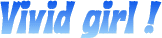「ただいま〜」
誰もいないはずの室内に向かって、絢子は玄関のドアを開けた時、そう声を掛けた。相模は不思議そうに首を傾げる。
「いつも帰った時は、そう言ってるのか?」
「そだよ。誰もいないけどさ、何となく『ウチに帰ってきた』って感じがするじゃない」
屈託無く笑う絢子を見て、彼は無表情に「そんなもんなのか…」と呟いた。
「上がってよ。何もないけど、広さだけは十分だからさ」
「お邪魔します」
礼儀正しくそう言ってからバッシュを脱いだ相模。絢子のちょっと面食らった表情に、眉を顰めた。
「なんだ?」
「あー、ううん。なんか新鮮だなぁって思って。お母さんが死んでから、斎とおじさんおばさん以外はウチに入れたことなかったから、なんかね……あははっ、ごめん」
じわっと込み上げてきたものを、無理に抑え込んで絢子は笑った。
「本当にいいのか? 俺なんかが上がって」
「いいの! 相模だから、上がってほしいんだもん」
うっかり本音を言ってしまい、ハッとなって口を手で押さえた絢子だったが、当の本人には伝わらなかったようだ。ホッとしつつも、鈍感な相模に少しだけ心が傷付く。
「と、とりあえず、そっちの部屋で適当に座ってて」
取り繕うような言い方で、彼女が指差した部屋はリビングらしい。日当たりのいい場所に頑丈そうなローテーブルがあり、その周りにクッションが固まって置いてある。相模はちょうど陽が差している場所に鞄を置き、フローリングの床に座った。
30インチほどはありそうなテレビに、ビデオデッキが2台とデジカメがコードで繋がっている。周囲に散乱しているテープのラベルには、去年のウィンターカップでの試合日が書かれていた。それを見付けた相模の表情が、少しだけ翳りを見せる。
「今お湯を沸かしてるからさ、もうちょっと待ってて。私は着替えてくるよ」
台所から出てきた絢子は、それには気付かず手を振りながら彼の前を横切り、奥の部屋に入っていく。
相模は鞄の中から英語の参考書を取り出し、しおりの挟んであるページを開いて読み始めた。ペンケースから蛍光ペンを出して、時折チェックをしている。
絢子がスウェットの上下に着替えて部屋から出て来ても、それに気付かず集中していた。彼女はそんな相模の様子を不思議そうに眺めていたが、真面目な彼ならこのくらいは集中して勉強するのだろうと思い、大して気にも留めずに台所へ消えた。
自分のと真新しいマグカップを用意し、沸いたお湯で好きな紅茶を淹れる。茶葉の入れ方やお湯の注ぎ方、蒸し時間など、普段自分が飲む時よりも遙かに気を遣って作った。かなり舞い上がっていることは、無意識に鼻唄が出ていることでも明らかだ。氷室がその場にいれば、苦笑を絶やさないことだろう。
湯気の立つマグカップと砂糖壷を置いたお盆を持ってリビングに行くと、相模はまだ参考書とにらめっこをしていた。その熱心さに、凄いなぁ、と単純に彼を感心しながら、絢子は我が物顔に鎮座しているローテーブルに、お盆を置いた。
その音で顔を上げる相模。
彼は読んでいた参考書を閉じて鞄にしまった。チラッと視線を走らせた絢子は、その表紙を見て思わず声を上げた。
「え? TOEFLなんて相模、受けるの?」
あまりにも驚いてしまったために、声がかなり大きくなってしまう。ちょっとばつの悪そうな彼の表情。
「あ、ごめん。ちょっとビックリしちゃって」
「いや……」
「えと、飲んで。お礼になるといいんだけど」
気まずい雰囲気を払拭するように、絢子は彼の前に力作の紅茶を淹れたマグカップを置いた。
「砂糖とかは……」
「いや、別にいらない」
相模は短くそう言って、カップを手に取る。かなり熱そうな湯気が立っているが、彼は特に気にした風もなくカップを口に近付けた。
自分らしくない、と思いながらも、絢子はドキドキする心臓を抑えつつ、彼が口を付けるのを固唾を飲んで見守っていた。が、相模は途中で手を止めてしまう。
「結城、なんか物凄いプレッシャーを感じるんだが」
「え!? あ、あははっ、ご、ごめん。その…他人に出すの初めてだからさぁ」
苦しい言い訳だ。絢子自身も思ったが、嘘ではない。幼馴染が来た時は、コーヒー党の彼の為に紅茶は自分のしか淹れないのだ。
「まぁいいけど。いただくよ」
「あ、うん」
先程の反省から、なるべく彼を見ないようにしているが、やはり飲んだ時にどんなリアクションをするか、大いに気になる。
カップの縁に口を付ける直前、嗅いだことの無い良い香りが、ふっと彼の鼻腔を刺激した。
「へぇ、紅茶ってこんな香りがするんだな」
相模の感嘆の声に、ぱぁっと絢子の心に花が咲いた。やった! と心中でガッツポーズを取る。
次いで、カップの中身を一口飲んだ。ちょっと驚いた表情になり、続けてもう一口飲む。
「ど、どうかな?」
「うん、美味い」
その言葉にホッとして、絢子はようやく自分のカップを持った。冷ますために、ふーふー息を吹き掛けている。
「ん? 結城って猫舌だったのか?」
「うん、だよ。あんまり温いとやっぱり美味しくないけど、ここまで熱いとちょっとね。相模は平気なんだ」
「あんまり考えたことはなかったな」
好きな相手のことは、些細なことでも知るのは楽しいものだ。それは絢子でも同じことで、彼女はウキウキした表情を絶やさない。
しばらくは二人で会話もなく、紅茶を飲んでいたが、その内に絢子が沈黙に耐えられなくなった。
「ねぇ、相模」
「ん? なんだ」
「…………」
声を掛けたはいいが、どう言葉にしていいか分からない。「あなたが好きです」と言ってしまえば楽なのだろうが、これでは屋上での高城を笑えない。彼がどんな気持ちで自分を呼び出して、どれほど緊張してあの屋上にいたのか。きついこと言っちゃって悪かったなぁ、と今更だが反省する。
「結城?」
蒼褪めた絢子をどう誤解したのか、相模は心配そうに覗きこんで来る。何か言わなければ! 焦った彼女の口から出たのは、
「さ、相模、さっきの参考書。なんでTOEFLの試験なんか受けるの?」
だった。ポンッと頭に浮かんだのが、さっきリビングで勉強していた姿だったので、つい言葉になってしまったのだ。後悔してももう遅い。
だが、相模の反応は……。
彼は絢子から視線を外し、考え込んでいた。何かマズいことでも訊いてしまったのだろうか? 絢子が困惑していると、小さく息を吐く音が聞こえた。
「まぁ、いつかは分かることだしな」
「え?」
「今の内に言っといた方がいいか」
「な、なんのこと? 相模」
独り言を言っていた彼が、怖いくらいに真剣な顔で自分を見たので、絢子はドキッとした。相模のこんな顔は、試合の時くらいしか見たことはない。
「俺、卒業したらアメリカの大学に留学するんだ。試験はそのための準備だよ」
初めて聞く話に、絢子の思考は停止した。