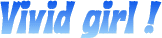暴れたら放り投げる、と言われ、まさか本気でやらないだろうと高を括ってジタバタしたら、彼の足が止まり両腕に力が入ったのを感じて、これは本気だ! と大人しくすることにしたのだ。
抱かれている本人はとんでもなく恥ずかしいのだが、相模のガタイと顔の良さで妙に絵になっているため、哂ったりする生徒は誰一人いなかった。それどころか、擦れ違う生徒たちはことごとく、「ほぅっ」とうっとりしたような表情をしている。本人たちがどう思っているかはともかくとして、傍目には美男美女のカップルに見えるのだ。これが氷室だったら、嫉妬と羨望の悲鳴の嵐になっていただろう。そうならないのは相模の人徳と言ったところか。
絢子は顔を覆ってしまっているために、自分がどんな風に見られているか知らなかったが、相模はしきりに眉を顰めたり首を傾げたりしていた。
そうこうしている内に保健室に着いた二人。
不在の札がドアに掛かっていたが、ベッドに寝るくらいなら問題はない。何しろ熱があって一人で歩くことすら儘ならないのだ。……と、相模は思い込んでいる。
一応ノックをして保健室に入る、律儀な彼。一通り中を見回して、ボソッと言った。
「誰も休んでいないみたいだな」
「……あのさ、相模。も、もうここで大丈夫だから、早く部活に行きなよ」
「そういう訳にはいかないだろ。さっきテーブルの足に引っ掛かって、転びそうになったじゃないか。いつもの結城なら、そんなドジはしないだろ。熱がある時くらい休んだってバチは当たらないさ。結城はいつもマネージャー以上の仕事してるじゃないか」
彼に言ってもらえることほど、絢子にとって嬉しいことはない。かぁ〜っと顔を真っ赤にして、彼女は相模の腕の中で小さく縮こまった。心の中では、こんなのは自分のキャラじゃない! と頭を抱えて呻いているのだが。
そんな絢子を見下ろして、クスッと優しく笑う相模。その微かな声が聞こえて、絢子は更に耳まで真っ赤にした。
「こ、こんなの熱じゃないから、寝てればすぐ治るよ。あ、あの……降ろしてくれる?」
「待ってろ、ベッドまで連れてく」
「そ、そんなことまでしなくても」
「っつっても、もう着いたけどな」
保健室の奥にあるベッドを囲っている白いカーテンを、相模は彼女を抱えたまま器用に開けた。
誰も寝ていないベッドだったが、それを見た絢子は、傍目にも分かるほど顔を強張らせた。相模にも、抱えている体が緊張したのが伝わってきた。
「? 結城? どうしたんだ?」
「…………」
無言で絢子は首を左右に振る。その表情は蒼褪めていて、さっきまでの様子とは別人の様に変わっている。
「結城?」
「……ごめん、病院のベッド、思い出しちゃって……」
「あぁ、そう言えば、病室の感じに似てるもんな」
ベッドが視界に入らないように、自分の腕の中で体を強張らせている彼女を見下ろし、相模は踵を返した。
「え……相模?」
「そんなじゃ、悪化させるだけだろ。家まで送ってくよ」
「ええ!? そ、そんなことまでしてくれなくても……」
「じゃあ、一人で帰れるってのか?」
そう言って、保健室を出た相模は彼女を廊下に下ろした。が、絢子は自分でも驚く程に足に力が入らず、相模にしがみ付いていないと立っている事も出来ないでいた。
「う、うそ……」
「だろ、結城の家、教えてくれれば送ってくぞ」
「……あ、ありがと」
こんなことは今まで一度としてなかった絢子は、自分の今の状況にかなりショックを受けていた。もう3年も経ったから平気だと思っていたのだが、あの出来事は彼女の心の奥底に、相当深い傷を残していたらしい。
「どうする? また、抱えていこうか?」
「い、いいいよ。支えてくれれば、何とか歩けそうだから」
いくら何でもお姫様抱っこは、もう恥ずかしい。自分の体重を考えれば、彼にだって相当負担を強いるはずだ。
色々と試した結果、相模が絢子の右腕に彼の左腕を絡めて歩くのが、一番いいらしいことが分かった。これはこれで、絢子の鼓動が激しくなる要因にもなるのだが、背に腹は変えられない。
傍から見れば、仲睦まじい恋人の様に見える二人は、一旦部室へと戻ってから着替えをし、絢子のマンションに帰ることにした。
**********
絢子のマンションは、冬泉学園から徒歩で10分ほどのところにある。相模は彼女が徒歩通学なのは知っていたが、どこにあるかまでは知らなかった。
制服の上からとは言え、絡めている腕から彼の体温が感じられて、絢子は終始心臓が口から飛び出るかと思うほど、激しい動悸をしていた。我が家であるマンションが見えてきて、漸くホッとする。
「あそこだよ。最上階の角部屋」
絢子が指差したのは、15階建てのこの辺では比較的大きなマンションである。周囲の建物はそれより低いので、見晴らしは良さそうだった。
「あの……もうここら辺でいいよ。ちゃんと、一人で歩けそうだから、さ」
腕を解こうとする絢子の手を、彼は止めた。
「相模?」
「どうせだから、部屋まで送ってく。途中で倒れたりしたら、俺が氷室に殺されるからな」
「は!? 何で斎が相模を殺すのさね!?」
「そりゃあ、大事な幼馴染だからだろ。さっきだって部活休んでいいから、結城を保健室に連れてけって、あいつが言ったんだぜ。なんで俺なのか、さっぱり分からないけどな」
「…………」
世話は焼かないと言ってたくせに、こうして二人っきりにさせてくれると言うのは、何か魂胆があってのことか、それとも気が変わったのか。
幼馴染の真意が読めない絢子だったが、高城のように、思い切って自分の気持ちを伝えた方が、後悔はより少ないのかもしれないと、ふと思った。
「……じゃあさ、お礼にお茶くらい出すから、ウチに寄ってってよ」
「さっきと言ってることが180度違うぞ?」
相模は突然の絢子の申し出に、驚いた顔で言う。
「大体、女の一人住まいの家に、男の俺が入れる訳ないじゃないか。それに、氷室が怒る」
「斎は怒らないって。私がお礼をしたいって言ってるんだから、受け取るくらいはいいんじゃないの? それに斎もたまに転がり込んでくるから、私は全然平気だし」
「それは幼馴染だからだろ。何にしても、俺はマズイ」
頑なまでに固辞する相模に業を煮やし、絢子は構わず彼の腕を引っ張った。
「もう! その住人がいいって言ってるだから、来なさいよ! それとも、私の出すお茶は飲めないって訳!?」
メチャクチャなことを言う彼女を呆れた表情で見下ろして、相模は溜め息をついた。
「はぁー、分かったよ。言い出したら人の言うこと、全く聞かないからな結城は」
「分かればいいのよ!」
ぐいぐい彼の腕を引っ張っていく絢子からは、先程までの昏い雰囲気はない。こういうことで元気になるならその方がいいか、と相模は心中で呟いた。