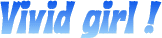冬泉学園には給食は出ないので、弁当持参か売店で買うか学食で食券を買って食べることになる。
我らがバスケ部の麗しき?マネージャー結城絢子も、クラスメートと一緒に学食へと来ていた。
さすがは有名私立校の学食。メニューはファミレス並みに豊富でバラエティーに富んでおり、味は高級レストラン並みに美味である。ついでに値段は、某ファミレスよりも更に安値だ。
女子のクラスメートが、パスタやオムライスなど一品物とコーヒーにデザートを頼んでいる横で、絢子はハンバーグのライスセットにラーメン、天津を頼む。
カウンターの中にいるオバチャンが、呆れた顔で
「あんたいつもいつも、よく食べるねぇ」
と感嘆して言うと、
「そりゃもう、快食快眠がモットーですから」
とニコッと笑って絢子は二つのトレイに乗った丼と皿を持って行く。オバチャンは目を点にして、それを見送った。
絢子は級友たちと一緒のテーブルに着き、幸せそうにモリモリ食べ始めた。他の五人の友人たちは慣れているのか、平然と自分のを食べている。周りの生徒たちは、絢子の旺盛な食べっぷりを見て、唖然としたり、げんなりしたりしていた。
中には美人なのに勿体ねぇ…などと思っている男子生徒もいるらしい。
そんな周囲の視線などどこ吹く風で、ひたすら食事に集中している絢子の元に、近付いて行く男子生徒がいた。
ずば抜けて高い身長に、強面顔。男子バスケ部の高城である。
「おい、結城」
何故か顔が赤い彼を、絢子は天津を頬張りながら見上げる。
「あにはね? はかぎ」
「話があんだ。食い終わったら、屋上に来てくれよ」
「ぼこの?」
もぐもぐと咀嚼しながらなので、彼女の言うことはイマイチはっきりしないが、高城には伝わってるらしい。
「ここの屋上で待ってる」
ごくんっと飲み込んだ絢子は、「いいけど、ここで言っちゃった方が早いんじゃないの?」と言うと、「んなこと出来るかよ!」
と怖い顔で怒鳴られてしまった。
そのエラい剣幕に目を丸くした絢子は、面倒くさそうに「分かったよ」と言い、高城はさっさと食堂を出て行った。
一体何の用事なのか。一人、腕を組んで首を捻る絢子を、級友たちは苦笑いで見ていた。
**********
そして15分後、絢子は約束通り屋上へとやって来た。待っていた高城は、柄にもなく緊張した面持ちでいる。
「一体何の用事さね? 高城。そんな深刻な顔似合わないよ」
ケラケラと笑う絢子に、高城は一層緊張した顔を見せ、逆に彼女の方がそれに驚いた。
「一体、どうしちゃったのさ? いつもの高城らしくないよ? 男はもっとドーンと構えてなきゃ」
「あのな……」
「うん?」
「お…………」
言い掛けて顔を真っ赤にした高城は、結局口を噤んでしまう。いつもの彼らしくないイジイジした態度に、ついに絢子がキレた。
「あ〜〜もう! 話があるんでしょ!? さっさと言っちゃいなさいよ! 自慢じゃないけど、私ゃせっかちなのよ!」
「だから、俺はお前が好きなんだよ!!」
「…………は?」
勢いに押されてと言うか、売り言葉に買い言葉で怒鳴る高城の告白。顔は不気味なほどに真っ赤に染まり、頭からは湯気を出している。
絢子はポカンと彼を見上げ、そして漸く口を開いた。
「えっと……それって、もしかして告白?」
「それ以外に何だってんだよ! マジメに聞けよな! こっちはシミズの舞台からダイブする気で言ってんだからよ!」
告白されてるこっちが何で怒鳴られるんだろう? と疑問を抱きつつも、絢子は冷静にツッコミを入れた。
「それを言うなら、キヨミズの舞台でしょ。せっかく告白してんのに、慣用句間違えたら恥だよ?」
「〜〜〜〜〜いちいちツッコミ入れんなよ! こっちは男の沽券掛けてんだ!!」
一世一代、カッコよく決めるはずだった理想の告白が、崖を転がり落ちるようにドンドン崩れ落ちていく。高城は、頭を抱えてダンダンと地団駄踏んだ。
絢子は溜め息をついた。
「悪いけど、あんたのことは、ただの男子バスケ部のレギュラーとしか見れないよ……あっ! それで、この前モ○バーガー行った時、あんなこと聞いた訳!?」
「そうだよ! 隠してたつもりだったのに、あいつらに全部バレバレだったし。お前はお前で煮え切らないこと言ってたし。だから、告白しようって決めたんだ! 俺だって必死なんだよ!」
いつもは強面で相手を威嚇するような目の高城が、泣きそうな顔で俯き、顔を真っ赤にして怒鳴る。絢子は困った顔で溜め息をついた。
「そりゃ、必死なのは見れば分かるけどさ。さっきも言ったけど、あんたのことは、何とも思っちゃいないよ。悪いけど」
「誰か、好きな奴がいるのかよ」
ギクッと絢子の肩が揺れる。先日のハンバーガー屋での失態といい、この手の話になると、彼女は精神的にかなり無防備になるらしい。
高城の脳裏には、先日の会話が事細かにリピートしている。
「やっぱりバスケ部の奴か?」
「……あんたに言う義理はないでしょ!」
ぷいっと横を向いて素っ気無く言う絢子の顔が、若干紅く染まっている。高城は、溜め息をついて苦笑した。
「俺、結城に振られたんだぜ。ちょびっとくらい、知る権利、あるんじゃねぇの?」
「…………」
「もしかしてさ」
その前置きに、絢子は冷や汗を流しながら、高城を見つめる。
「氷室、か?」
先日、氷室本人に否定されたとは言え、高城は一番可能性があると思われた名前を挙げる。それを聞いた瞬間、絢子はあからさまにホッとした表情をした。何故か、その表情に彼はショックを受けた。
「やだな、違うよ。斎とは何でもないって。ただの幼馴染さね」
笑いながらパタパタと手を振って言う。
「話がそれだけなら、私ゃもう行くよ。あ、振られたからって、放課後の部活休むんじゃないよ!」
手を腰に当ててビシッと指差して釘をさし、絢子は背を向けて校舎へと入っていく。高城は肩を落として、彼女の後ろ姿を見送った。
彼の中で、一つの恋が、終わりを告げた。