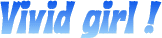ジャージを着た腰に手を当て、絢子は「ふぅっ」と息を吐きながら、紫に介抱されながらドリンクを飲んでいる松永の元に行った。桂木と金井は放って置いても平気だろう。
「松永、気分はどう?」
「あ、絢子先輩」
近付いてきた絢子に、紫がペコッとお辞儀をする。松永は吐いたせいで蒼白い顔をしているが、特に変った様子もなく、ドリンクを飲むのに集中している。が、表情はかなり暗い。落ち込んでいると言ってもいいくらいだ。
絢子が傍らに座り込むと、松永はビクッと体を揺らして彼女を見、そしてむくれたように下を向いた。そんな彼を見て、苦笑しながら言う。
「松永、初めてじゃあんなもんさね。でもま、結構やった方じゃない? 課題は山積みだけど、あんたの根性は買ってあげるよ。先ずは、この程度で吐かない体力を付けるのが先決だね。明日からみっちり体力作りのメニューを出してあげるから」
ニコッと笑って言う絢子に、松永の見せた表情は・・・・・・見る方が気の毒になってしまうくらい泣きそうな顔だった。
「何ビビッてんの! 言っとくけどね、原田のあのバケモノじみた体力は、私の特別メニューを一年の時からこなして来たからだよ。あいつに追い付けとは言わないさね。ただ、試合中に何が起こっても対処できるだけのスタミナを付けろってこと。スキルもそりゃ必要さね。でも、先ずは体が第一だからね。この一年で 20センチも背が伸びたんだから、それに見合う体力付けなきゃ」
聞いている間中、紫はポーッと頬を赤らめて絢子を見ていた。普通のマネージャー以上の働きをする絢子は、彼女にとっては憧れ以上の存在のようだ。
ふいっと顔を背けた松永は、不貞腐れている。が、それは尤もな絢子の意見に対してであり、吐いてしまった自分に対しての自己嫌悪から来る表情だった。
「さて、そんじゃ、これ片付けますか」
立ち上がった絢子が、嘔吐物の入ったバケツの取っ手を持ち上げたのを見て、紫が慌てて止める。
「絢子先輩! あたしがやります! 先輩にそんなこと、させられません」
「いいよ、これくらい。おりょ?」
笑いながらパタパタ手を振る絢子から、バケツを奪った人物がいた。
「松永?」
「俺がやる。俺のだから……」
「ん、そんじゃ任せるよ。紫ちゃん、バケツの置いてあった場所は?」
「あ・・・体育館の用具室です」
「だってさ。じゃ、後よろしくね。紫ちゃん行こうか、まだまだ私らにゃ、仕事があるんだから」
そう言い置いて、絢子は素っ気無く松永に背を向けた。気後れしながらも紫はその後を追う。だが、これは絢子なりの気の遣い方だ。男としてかなり自己嫌悪に陥っている松永には、一人にさせてやる方が落ち着くだろうと、思ってのことだった。
そして行った先は金井と桂木の所。
「金井! あんたねぇ、もう少し体力付けな。ポイントゲッターが簡単にガス欠起こすようじゃ、困るよ」
「・・・すみません」
「明日から松永と一緒に特別メニューこなしなさいよ」
げ・・・と思ったかどうかは定かではないが、金井は若干嫌そうな顔をした。
「それと、毎日牛乳飲んで、魚と鳥の骨…えっと軟骨か、食べること! カルシウムを強化すれば、それだけ運動してんだから背は伸びていくよ」
「牛乳は飲んでるんですけど・・・」
「牛乳だけじゃダメってことさね。魚、嫌いだって聞いたけど?」
「う・・・」
「出来れば光り物がいいんだけどね」
「うぅ・・・」
絢子から指摘されるたびにギクッとなる金井を、紫と桂木は心底気の毒そうに見ていた。が、思わぬお鉢が回ってきて、桂木はたじろいだ。
「桂木! あんたもだよ! せっかく類い稀なジャンプ力があるんだから、それを更に生かすために背を伸ばしな」
「お、俺までかよ!?」
自分を指差す桂木に、絢子は腕を組んで胸を張って言った。
「当然! 言っとくけど高城と相模と斎にだって、特訓は課すんだからね!」
「分かったよ」
ムスッとしながらも承諾するのだから、彼も絢子のことは認めているのだ。
はっきり言って氷室と絢子と相模がいなかったら、冬泉学園高等部の男子バスケ部が昨年の全国大会やウィンターカップに出られることはなかった。それは多分に絢子の存在が大きい。コーチ役までこなせるマネージャーは、そうそうはいないだろう。
「よし!」
と満足そうに頷いて、絢子は平部員の練習を見に行った。紫は後を付いて行きつつ、彼女の颯爽とした後ろ姿を見ながら、素敵だなぁ…といつもの如く感銘を受けた。
「あ、紫ちゃん」
おもむろにくるっと振り返られ、紫は心臓が口から飛び出るくらい驚いた。
「な、何ですか? 絢子先輩」
「紫ちゃんは紫ちゃんの出来ることをするんだよ。私だって、私の出来ることをしているだけなんだからね」
「で、でも・・・。絢子先輩の出来ることは、凄いことばかりですから・・・」
下を向いてボソボソと話す彼女に、絢子は言った。
「紫ちゃん、私を見てくれる?」
「は?」
紫がポカンとして顔を上げる。
「んで笑って」
「え? えっと…こうですか?」
ニコッと笑った紫の笑顔は、とんでもなく可愛いものだった。近くでパス練習をしていた平部員が、顔を赤らめてボールを取りこぼすくらいの威力だ。
うんうん、と嬉しそうに頷く絢子に、紫は不思議そうな顔をした。
「あの、これが?」
「その笑顔ってさ、紫ちゃんにしか出来ないんだよ。男って結構単純だから、紫ちゃんのその笑顔を見るために頑張って試合に勝つってくらい、しちゃう生き物なんだよね」
「はぁ・・・」
「それは私にゃ絶対出来ないからね。正直、可愛くて羨ましいと思うよ」
思い掛けない言葉に、息を呑んで恥ずかしそうにモジモジする。
「そんな・・・絢子先輩だって、とても綺麗です。あたしは先輩の笑顔とか、好きです・・・」
うつむく紫の頭に手を乗せて、絢子は優しく撫で撫でした。
「あはは、そう言ってくれるのはありがたいけどね」
「ほ、ホントです」
「うん、ありがと。まぁそれは置いておくとして。私がこんなこと出来るのはさ、偶然ていうか・・・言ってみれば『好きこそ物の上手なれ』っていう奴だよね。たまたま見たNBAでバスケに転んで、斎がやってるって知ってあいつの試合とか見るようになって、ルールブックやら雑誌やらを読みまくってね。で、それだけじゃ飽き足らずに、テレビのNBAの試合を見たり、ウチが出てなくても関東や全国大会の試合見に行ったりしてさ、それで何となく分かるようになったって言うだけなんだよ。それにさ、いい男がカッコイイプレイするの見るの、楽しいじゃない。だから、みんなにそれをやらせようってだけなのよ。不純っしょ? そんなんだから、本当はあまり褒められたモンじゃないのよね。あ、今のはオフレコね。斎は知ってるけど、高城とか知ったら煩いから。相模は真面目だしね」
おどけるように言う先輩の姿に、紫はひたすら頭が下がる思いだった。
彼女の知っていた絢子には、そんな努力をしてきたなど、露程も見せたことはなかった。不純だとは言うけれど、そのためにどれ程の努力をしてきたのか。その結果彼らは強くなり、高校バスケ界で一躍有名にもなったのだ。
「あたし、まだまだダメですね」
「どうして? 紫ちゃんはよくやってるよ。私らが引退するまでに、役に立つことはマニュアルにして残してあげるからね。これからも頑張って、サポートしてね」
「はい!」
元気良く返事をする紫に、満足そうに頷いた絢子は、目の端に体育館の済みでサボっている部員を見付けた。ヒクッと口元を引き攣らせた彼女は、彼ら目掛けてダッシュする。そのスピードは、レギュラーも目を剥かんばかりの速さだ。
「おらーそこぉ! サボってじゃないよ!」
本日二度目の結城絢子様の跳び蹴りは、見事なまでに床に座って駄弁っていた3人を、一発で仕留めたのだった。
これだけはどう頑張っても真似は出来ないと、紫は改めて絢子の偉大さ(?)を思った。
**********
保健室に連行された原田は体温を計った結果、何と38度9分も熱があり、めでたく問答無用でベッドに寝かされたのだった。
「ったく! 体の調子が悪い時は言え! 俺はそこまで鬼じゃねぇぞ!」
と氷室に散々に怒鳴り散らされ、彼は大人しく布団に包まったという。
本来ならまともに歩けるような熱ではないのだが、鈍感なのか鍛えた成果か、保健医からもらった解熱剤を飲んで1時間寝た後には、しっかりした足取りで体育館に姿を現した。
部活を続ける、と言う原田をレギュラーと絢子が総出で「やれるか阿呆!」「さっさと熱を完璧に下げて来い!」と散々罵倒し、彼はすごすごと学園を後にした。
「あ、そうだ!」
部活終了後、絢子が思い出したように言い出した。
「今日の試合ね、ビデオ撮ってたでしょ。あんたたち全員にダビングしてあげるから、それ見て研究しなさい」
と言いながら、やたらとニコニコ笑う彼女に、氷室以下その場にいたレギュラー全員、寒気を覚えた。
そして渡されたビデオを見て、彼らは大いに落ち込み、泣きながら「結城、覚えてろー!」と星に向かって雄叫びを上げたと言う。
勿論、ご近所様から「煩い!」と苦情が来たのは言うまでもない。