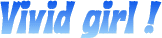コートチェンジをして8分が経過した。
ゲーム時間は残り2分。3on3でのオールコート、しかも休憩なしのせいか、通常の試合の時よりもかなりバテて来ているのが分かる。
試合形式の練習が初めての松永は勿論のこと、体力バカの高城や部長の氷室も、全身汗だくになって苦しそうな呼吸を漏らしている。顎の先から落ちる汗を、拭う気力もないほどだ。6人とも着ているTシャツは、汗を吸って体に張り付き、更にポタポタと裾から汗が滴り落ちていた。
体力の無い金井は、膝を床に付けてもう一歩も動けないような状態だった。だが、そこはちょうど彼らのゴールポストの近く。それもおあつらえ向きに、3ポイントラインの外だ。
「金井! そこから動く必要はねぇから、俺らが回すボールを、必ずシュートしろ!」
ボールをキープしている相模のマークに付きながら、原田が掠れた声を上げる。彼自身、息も上がってしゃべるのもキツイくらいだが、3人の中では一番レギュラー暦が長い。必然的に彼がPGを務めることになったが、何しろ初めてのポジションの上、相手はストリートでもチームを組んでいるバスケ部のベスト3だ。それだけでも彼のプレッシャーは並大抵の物ではないのだから、そんな中で10点差に食らい付いているのは、かなり凄いことなのである。
原田は目の前でドリブルをしながら、抜くタイミングを計っている相模を見た。自分と同じ時間動いているはずだが、そして同じポジションのはずなのに、彼の方がまだ体力的に余裕がありそうだ。少なくとも、原田の目にはそう見えた。
正直、悔しいと思う。持久力なら高城以上に自信があるのに、今はもう立っているのもツライほどにバテているのだ。
「相模!」
背後から氷室の声が聞こえた。相模の視線が原田から見て左側に流れる。
パスか? と思い、重心が左に動いた瞬間、相模は右側を抜けて行った。最も単純なフェイク。しまった! と体を反転した時、軸にした右膝がガクッと崩れた。体力の限界。まさか自分が? と思う。
かろうじて膝を付くことは避けられたものの、相模の後ろ姿を見る自分が情けなかった。
ゴールに迫る相模に松永がディフェンスに付いた。金井の次にバテバテの彼だが、根性で食らい付いた様だ。が、それをあっさりとノールックでゴール下にいる高城へパスを送られる。完全に虚を付かれた松永には、相模の手からボールが消えたように見えただろう。
パスを受け取った高城は、「おりゃ!」と言う掛け声と共に、豪快なダンクシュートを決めた。
これで65対53。3ポイントシュートなら4ゴールで追いつく点差だが、金井の体力と残り時間を考えると難しい。
松永がスローインポジションに付く。原田も立ち上がった。自分でもおかしいくらいに、膝が笑っている。が、気力で体を奮い立たせて、松永からのボールを受け取る。足があまり上がらなかったが、それこそ気力だけでドリブルをしながら走る。
松永は付いて来れないようだが、それを案じる余裕は原田にはもうない。とにかく、金井に繋げてシュートを託すだけだ。
行く手を遮る氷室が邪魔だ。疲れているはずになのに、そうは見えない。激しい呼吸と汗だくの顔は、同じ男から見てもやけに色っぽく見える。これなら女子共が騒ぐのも当然だよな、と熱で茹だる頭で原田は思っていた。
さっき相模のやったフェイクが、彼の脳裏にまざまざと蘇る。何も考えず、そのイメージだけを追って原田の体が動く。信じられないことだが、氷室はそれに引っ掛かった。絢子もビデオの中で、「原田、今のマジで上手いよ! そのタイミングと技、忘れないようにね! 斎、いくら疲れてるからって、そんな単純なフェイクに引っ掛からないでよ!」と若干興奮気味に言っている。
氷室を抜いた原田に、高城が慌ててマッチアップに付く。
「金井!」
原田の振り絞った声に金井がピクッと反応する。高城の足の間を抜けてきたバウンドパスを、体勢を立て直して金井は受け、その場でシュートを狙った。相模がシュートコースを塞ぐが、金井の目にははっきりとシュートコースが見えていた。
ザッと音を立ててリングを通り抜けたボール。
ピーッ! 桂木の笛が甲高く鳴り響く。
「みんな、試合はそこまで!」
それに重なるように絢子の声が聞こえた。
刹那、ドサァッと重い物が落ちる音がする。原田が気を失って床に倒れ込んでいた。それを見て松永が、ガクッと両膝を折る。金井もペタンとその場に尻を付いていた。
相模が急いで原田の元へ行き、高城も金井の傍にしゃがんで声を掛けている。
「紫ちゃん、バケツ持って来て! どこからでもいいから!」
「は、はい!」
切羽詰った絢子の口調に、紫が弾けれたように用具室へと走る。
「桂木! タオルとドリンク、3人分持って来て! 斎、相模、高城は自分でやりな!」
言われた桂木はすぐさま、時計を止めてタオルとドリンクボトルを取りに走った。氷室はドリンクボトルをタオルで巻いて、高城と相模に投げて寄越す。
異様な雰囲気に、コートチェンジの際に通常練習に戻っていた部員たちが、ギョッとして不安そうにレギュラーのいるコートを見た。
絢子はその部員たちに素早く視線を走らせた。
「橋本! 救急箱のところに酸素があるから持って来て!」
救急箱の置いてある場所に一番近い部員を、瞬時に見て取って指示を出す。まるで怒鳴られるように言われた2年の橋本は、ビックリして持っていたボールを落としてしまい、オロオロしながらも酸素ボンベを持って行く。
「絢子先輩!」
「サンキュ、紫ちゃん」
そう言って絢子は彼女の持って来たバケツを持って、松永のところへ飛んでいった。彼は両膝を床に付き、右手で口元を覆って左手は屈み込む上体を支えている。絢子が顔のすぐ下にバケツを置いた直後、彼はその中へ思いっ切り嘔吐した。
苦しげに吐き続ける松永の、汗でシャツの張り付いた背中をさすってやる絢子。
「あぁ、大丈夫。ちょーっと体力使い果たしちゃっただけだよ。初めての試合形式で緊張したんでしょ。…紫ちゃん」
自分を心配げに見ている後輩を呼び、後を任す。
「悪いけど、介抱してやって。斎! あんたも手伝いな!」
ふわふわのタオルで顔の汗を拭い、ストロータイプのためにちょっと苦しい思いをしながらドリンクを飲んでいた斎は、やれやれと紫の元へ歩いていく。首に掛けたタオルの端で、まだ流れ落ちてくる汗を拭きながら、桂木が持って来た松永のドリンクを持って行く。
絢子は紫と入れ違いに橋本から酸素を受け取り、倒れている原田の元に急ぐ。彼のところには既に相模がいて、自分のタオルで気絶した原田の汗を拭ってやっていた。
「ありがと、相模。疲れてんのに、悪いね」
「いや、俺なら大丈夫だ。原田のことも見てやるから、結城は金井を見てやれよ」
相模は絢子から酸素を受け取り、息も絶え絶えに呼吸してる原田の口元に当ててやる。何度か酸素を送り込んでやると、大分呼吸が楽になったようだ。それでも、顔が火照っているのは中々治まらない。
「あ、金井は……」
見れば、床にへばった金井には桂木と高城が行っている。自分でドリンクを飲んでいるので、多分状態は大丈夫なのだろう。
「金井は大丈夫だよ。それより原田が一番心配。氷を取ってくるよ」
「あぁ」
絢子は走って保健室へと向かった。
原田は多少呼吸が荒いものの、先刻よりは穏やかな表情になっている。相模はホッとして、未だ口を付けていなかった自分のドリンクを飲んだ。原田のも勿論預かっているが、気を失ってる相手にどう飲ませるか……。
暫し考えた結果、原田のボトルの蓋を取って彼の頭を持ち上げ、強引に口を開けさせた。その中に冷たいドリンクを少量流し込む。口の中の液体が嚥下しやすいように、少しだけ頭を落としてやると、ゴクンッと飲み込んだ原田は咳き込み、うっすらと目を開けた。それを覗き込む相模。
視界が定まらないのか、ぼやっとしていた原田は、突然ギョッとして起き上がった。
「さ、相模!?」
オッ? と相模が思った瞬間、原田は頭をぐらつかせて、再び仰向けに倒れた。
「いきなり起きると危険だぞ」
「そういうことは先に言ってくれ……」
眩暈を起こしてしまった原田は、ヨレヨレとゆっくり尻を床に付けたまま体を起こす。
「お待たせ、相模! おりょ? 原田起きたんだ?」
「何かいきなり噎せたんだよ。相模、俺に何しやがった?」
「ドリンクを飲ませただけだ。噎せたのは少し気管に入ったからだろ」
一体どんな飲ませ方をしたのか、原田は恐ろしくて訊く気にもなれなかった。勿論、教えてやるお人好しは誰もいない。
「ま、いいか。ほい、原田。冷たいよ」
そう言って絢子は、保健室からもらって来たポリ袋に入った氷を、ぴとっと原田の首筋にくっつけた。一瞬、体をビクッとさせた原田だが、すぐに気持ちよさそうな声を上げる。
「うわっ、スッゲ気持ちいいぜ〜」
みるみるうちに氷が溶けていくのを見て、逆に絢子の方が驚いた。
「ちょっと原田、あんたもしかして、凄い熱があるんじゃないの!?」
彼女の言葉に反応して、相模が左手を自分のおでこに、右手を原田の額に当ててみる。氷室もその声を聞きつけてやって来た。
「どう? 相模」
「・・・保健室に連れて行くのがいいかもな」
それにギョッとしたのは他でもない、原田本人だった。
「へ? 俺、熱なんてねぇって! 熱いのはぶっ通しで試合してたからだろ!」
「お前、もしかして風邪引いてたのか?」
背後に立つ部長が、腕を組んで冷ややかな視線で見下ろしている。風邪引きの部員に、休憩なしで試合をさせたとあっては、責任問題に発展しかねない。
「引いてねぇ!」
「高城!」
絢子の呼び声に、高城がどこか嬉しそうな顔でやって来た。金井は普通に立っているので、もう大丈夫だろう。
「何だよ、結城」
「原田を保健室に連行して」
「は? 何で俺が!」
「だから俺は何ともないって!」
高城と原田の抗議が重なった。が、絢子は聞く耳持たない。
「あんたが一番力があるからだよ。斎にも行かせるからさ。いいよね、斎」
「当然だ! ほら、行くぞ」
氷室に腕を掴まれて、原田は渋々立ち上がった。途端に足元がぐらついてよろめく。高城が慌ててもう片方の腕を取った。
「あれ?」
「あれ? じゃねぇ! まともに立てねぇじゃねぇか!」
「氷室、耳元で怒鳴るなよ。……ったく」
「あぁ、それでか」
唐突に相模が呟き、連行する者される者、そして絢子が彼を見る。
「相模、何?」
「俺たちの中で一番持久力のある原田が、途中でスタミナ切れ起こしてたろ。おかしいな、とは思ってたが、熱があるんじゃあ当然だよな。安心したぜ」
「安心って、何でだよ?」
「気になるだろ。普段、2〜3時間はぶっ続けで部活していても平気な奴が、たかが20分の試合でバッテリー切れ起こすなんて。初めてのポジションだとか、原田はそんなプレッシャーで潰れるような奴じゃない」
冷静な相模の言葉に、「そう言われればそうだ」と、誰もが納得した。
「んじゃ、斎、高城、よろしくね」
バイバイ、と手の平を見せて振る絢子を尻目に、3人は保健室へと向かった。