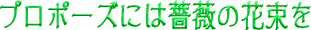春の温かな日差しの中、彰人の運転する車は安全運転で、山の麓にある湖にやってきた。すぐ目の前は山という、なかなかのロケーションであるが、朔は外の景色にはあまり興味がないようで、ナビシートから身を乗り出すようにして、計器類などを覗き込んでいる。
「そんなに面白いですか? 朔」
「当たり前じゃん! ポルシェなんか滅多に乗れないからな」
彼女の、こんなウキウキした様子は初めて見る。
しかし彰人には、こういうものに興味を持つ、朔の気持ちがよく分からないでいる。
「あなたならポルシェくらい持てるでしょう? 何故買わないのです?」
彼の疑問は当然だ。篠原家は真條家と同程度の財力を持っている。ポルシェの新車くらい、彼女のポケットマネーで買えるはずだ。
その彼女の返答はといえば……。
「そりゃ買えるけどさ、外車でバトルなんか出来ないじゃん。フェアじゃないもん」
「バトル?」
ハンドルを握りながら、彰人はクエスチョンマークを頭上に飛ばす。
「あれ、知らないか? 峠道でさ、早さを競うんだよ」
「…………?」
走り屋同士の峠のバトルなど、間違っても知っている彼ではない。峠道で早さを競うと言われても、全く想像すら出来ない。
「何の早さを競うんです?」
「だからさ、上りや下りでどっちが早く着くか競争するんだよ」
「…………」
「ま、後で実体験させてやるって」
上機嫌で朔は、彰人の肩をポンと叩いた。何故か、叩かれた肩からゾクッと寒気がしたが、彰人は気のせいだと思ったようだ。
車は湖の駐車場に停まった。土曜日であるためか観光客も多く、関東ナンバーの車が半数近く見えた。
「真條って運転上手いよな」
エンジンを止め、キーを抜いた瞬間おもむろに褒められ、彰人は怪訝な顔で恋人を見やる。
「そうですか?」
「うん。高速降りてから山道走ったじゃん。コーナーもスムーズだったし、シフトも上手い。俺、普段は自分で運転するだろ。だから他人の運転する車って酔っちゃうんだけどさ。でも、今日は山道なのに全然平気だったぜ」
嬉しそうに話す朔に、彰人の顔も綻んだ。
「それは、光栄ですね」
そう言って彰人は、未だ大人しく助手席に収まっている彼女の右手を取り、その甲に恭しくキスをした。
途端に頭から湯気を出し、口をパクパクさせて固まる朔。せっかくの美貌がもったいないほど、ユデダコのように顔を真っ赤にしているが、それを見て彰人は満足そうに微笑んでいる。
「う……おっ俺、先に降りて、る、な」
朔は喘ぐように言うと、モタモタしながらシートベルトを外し、逃げるように車を出た。
「やれやれ、朔を『女性』にするには、やはり時間が掛かりそうですね」
溜め息と共に呟いた言葉は、内容とは裏腹に楽しそうだった。
ゆっくりと車から降りると、朔は遊覧船乗り場近くの柵に、もたれるような形でへたれている。
今日もジバンシーのメンズスーツで決めているため、見た目には男前の好青年だ。周囲の人々、特に女性の視線を釘付けにしている朔だが、いくらイケメンでも挙動不審では誰も声を掛けようとはせず、遠巻きに見ている
彰人は苦笑いを浮かべて、そんな彼女に近付いた。うずくまる塊の傍まて来ると、朔はピクッと肩を揺らす。
「大丈夫ですか、朔」
声を掛けられたものの、それが笑いを含んでいると分かり、朔は憤然と立ち上がった。
「大丈夫じゃない!! 真條がっへ、変なことするから!!」
「手の甲にキスしただけですよ」
「笑いながら言うな!」
「早くあなたに、女性として扱われることに慣れてほしいですからね」
「…………っ!」
真っ赤な顔でわなないた朔が、文句を言おうと口を開いた瞬間、彰人に口付けされてそれは叶わなかった。
明らかに女性と分かる2種類の悲鳴と、動揺するざわめきが周囲から上がる。
鼻先に見える彰人の端正な顔。閉じたまぶたに長い睫毛が伸びている。朔が瞬きをしている間に、彰人は離れてしまった。
「なっ…なっ…」
更に顔を赤らめて慌てふためく朔を、彼はクスクス笑いながら見下ろしている。
「い、いきなり何すんだよ!? ちゅ、注目浴びてんじゃねぇか」
周囲からはしきりに「ホモ!?」だの「初めて見た!」だの、ざわめきが絶えない。中には「見ちゃいけません!」と子供を叱る母親らしき声もあった。しかし、そんな外野のざわめきも、彰人はどこ吹く風。
「朔が女性らしくなれば、これらの声も変わりますよ」
「…………」
痛いところを突かれて朔はぐうの音も出ないが、つい一週間前の彰人の言葉を思い出した。
「むう……なんだよ、俺の好きにしていいって言ったじゃんか!」
「ええ、言いましたが、撤回することにしました」
「はっ!? ずるいぞ!! 男に二言はねぇだろ!!」
「それを言うなら、武士に二言はない、ですよ」
「いちいち突っ込むなよ!! 男だろうと武士だろうと一緒じゃんか!」
「私は武士ではありませんので」
「屁理屈!!」
「はははっ普段はそれでも構いませんが、私と二人でいる時くらいは、女性らしい格好をされては如何です? あれほど美しく変身出来るのも、一つの才能ですよ」
「う、うつくし……」
親はともかく、身内以外から『美しい』と言われたことなど、とんとない朔である。それも好きな男から言われたこともあって、彼女は頭から湯気を出してよろめいた。
「朔? 大丈夫ですか?」
「…………」
下を向いてボソボソと呟く朔の声は、しかし、彰人には届かなかった。
「え? なんですって?」
彼女の口元に耳を近付けたところで、「真條のとうへんぼく!!」と怒鳴られ、キーンと響いた耳を押さえている間に、朔はズンズン歩いて近くの土産物屋へと入って行った。
**********
バトルをする前に一度は運転しておきたい、という朔にハンドルを持たせ、二人は本日宿泊するホテルへとやってきた。
東京の都心とまではいかないが、そこそこに開けた都会である。彰人が取ったホテルは、この街で唯一のリゾートホテル。わざわざロイヤルスウィートのあるホテルを選んだのは、もちろん朔とイチャイチャするためである。
朔の方は、そんな恋人の思惑など気付きもせず、上機嫌でリビングのソファに座った。こう見えて結婚願望のある彼女は、それなりに綺麗で女性受けする部屋が好きなのだ。
しかし、これみよがしに長い足を組む姿は、とても女には見えず、荷物を持って来た女性のコンシェルジュは、興味津々な表情で朔と彰人をチラリチラリと見ている。
誤解をしていることは一目瞭然だが、彰人はあえて訂正はせず、彼女に労いの言葉を掛けて、さり気なく部屋から追い出した。彼女が出て行くのを確認して、彰人が朔の隣りに腰を下ろす。
「…………真條」
「なんです? 朔」
「なんか、凄ぇ近くないか?」
気のせいではなく、彼は背もたれに肘を付き、体を朔の方に向けている。しかも彼の胸の辺りが朔の肩に当たっている。朔の逆側にはソファの肘掛があるため、逃げようにも逃げられない状態だ。
「夜は峠に行きたいと、言っていたでしょう?」
「う… ああ、言ったけど……っ」
思わず背けた顔を、彰人によってこちらに向かされた。頬を押さえる彼の大きな手。
間近に迫る彰人の端正な顔から視線を外す朔だが、押さえられた頬を上向かされて、まともに見る形になってしまう。
男と見つめ合う経験などまるでない朔は、耳まで真っ赤になっている。それがあまりにも可愛過ぎ、彰人はクスッと笑った。
「な、なんだよ!」
「可愛いですよ、朔」
「なっんっ」
言い掛けた言葉を、またしても彰人の唇で塞がれてしまう。しかも、今度は舌まで入れられた。
その感触に慣れない朔は、ビクッと体を震わせて身を捩らせる。だが、彰人はそれに合わせて自身の体や顔を巧みに動かしていく。
気が付いた時には、ソファの上で彼に組み敷かれた格好になり、全く逃げられなくなってしまった。
「ちょっ……しんっ」
「なんです? 朔」
ようやく唇が解放された時には、息が上がり、心臓も張り裂けそうなほど鼓動が早まっている。
喘ぐように呼吸する朔に対し、彰人は憎らしいほど涼しい顔だ。
「ま…まだ昼間っじゃんか」
「もう夕方ですよ」
「で、でも……食事もあるしひゃっ!」
肩を押さえ付けていた彰人の手が、胸に降りて来て揉まれた。朔は全身が火照るのを自覚しながら、慌てて上にある彼の体を押し上げようとするが、さすがにビクともしない。
「あなたが、夜は走りに行くと言ったでしょう」
「言ったけど……やっ!」
背中に回っていた手が太股の内側を撫でて来て、朔は慌てた。
「ですから、今の内にあなたを頂いておこうと思いまして」
「どーゆー理屈ちょっ真條!」
胸にあったはずの左手が、いつの間にかシャツのボタンを外し始めていた。
「ちょっ待っやっ」
開いた胸元に彰人の唇が降りて来る。
「わ、分かった! 分かったから! 夕食までしていいから! だから、シャワーくらい浴びさせてくれ〜!」
半泣き状態の朔から顔を離した彰人は、優しく微笑んでゆっくりと体を起こした。
朔がホッと安堵したのも束の間、今度は体が浮き上がる。思わず手近にあるものに抱き付いたが、それは彰人の頭だった。
「え!? 真條!?」
「では一緒に入りましょうか」
「はあ!? な、なに考えてんだよ、スケベ!!」
「男はみなこんなものです」
「う、嘘だ!! 笑いながら言いやがって!」
腕の中でジタバタ暴れる朔の耳元に顔を近付けた彰人は、そっと囁いた。
「静かにしないと、また足腰立たなくなるまで、可愛がって差し上げますよ」
「…………っ!!??」
体中興奮で真っ赤だった朔が、一瞬で青褪めた顔に変わった。口をパクパクさせて、息をするのも忘れている。
朔の脳裏に甦る、二度目のデートの夜。
彰人に誘われて再び彼のマンションに行ったのだが、その夜、本当に足腰立たなくなるまで可愛がられてしまったのだ。
プロポーズの日は、初めてなこともあって手加減してくれていたことを、身をもって知った朔だった。
今日はせっかくポルシェで心置きなく走れる日。それをこんなことで潰したくはない。朔は渋々、彼の腕の中で大人しくなった。
「よく出来ました。ご褒美に優しく抱いてあげますよ」
「…………子供じゃない!」
拗ねる朔の額に、愛しそうに唇を落とした彰人は、またもおかしそうに喉の奥で笑った。
「では姫様と呼んだら、応えてくれますか?」
「ひっ!?」
「冗談です」
「!?」
しれっとぬかす彰人を下から睨み上げ、朔はプイッと横を向いた。
「真條のバカ」
「バカと言う方がバカなんですよ?」
「…………」
朔はもう何も言わず、ムッとした表情で更に横を向いた。
彰人もからかうのをやめ、彼女を抱き抱えたままバスルームへと消えた。