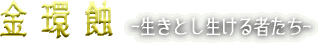「ねぇ、お兄さん。あたしの体、暖めてくれない?」
寒さも極まる2月の東京。人通りの多い渋谷の裏通りは、人々の吐く息で引っ切り無しに白くなっていた。
黒いロングコートの透の腕に手を伸ばし声を掛けたのは、未だ幼さの残る面立ちの少女だった。透を見上げる顔は、寒さだけが原因ではないだろう。頬が赤く染まっていた。
「もちろん、あたしもお兄さんを楽しませてあげるよ? ピチピチの17歳の体を、1回2万で抱けるの。安いでしょ」
にこっと自信あり気に笑う口元からも、吐き出される息は白い。暖かそうなコートに、ストッキングの足を剥き出しにしたミニスカートとショートブーツ。少女が金に困っている様子は全く見られなかった。
何も言わない透に何を感じたのか、少女は艶然と微笑みながら、彼の左腕に自分の両腕を絡ませた。
「あたしさぁ、人肌恋しいんだ。イケメンなお兄さんになら、抱かれてもいいよ? ちゃんと気持ち良くさせてあげるから、ね?」
媚を売るように上目遣いで誘ってくる。これで落ちなかった男はいない、とでも言いたげな微笑みである。
「でも、ちゃんとお金を払ってくれなきゃダメ。お兄さんの着てるコート、結構物がいいでしょ? あたしの目は誤魔化せないからね。お金持ってるって、分かるんだから」
語尾にハートマークを飛ばすほどに、甘い口調で囁く。そこで初めて透の表情が動いた。まるで少女を挑発するような、どこか蔑んだ微笑みだった。
「俺をその気にさせられるのか?」
「あら、言うじゃない? あたしの挑発に乗らなかった男はいないんだから」
そう言うと、少女は絡んでいた透の腕を引っ張って、近くのラブホテルに連れて行った。
高い部屋を選び、そこに入ってドアを閉めるや否や、透の顔を両手で包み込み赤い紅の唇で彼のそれにむしゃぶりついた。唐突に濃厚なキスをされても、透は慌てることなくそれを受け、少女の好きなようにさせた。
これまでキスだけで、簡単に男を落としてきた少女だったが、透には勝手が違うことを早々に見抜いたようだ。
「大抵の男は、これで落ちるのよ? お兄さん、慣れてるのね」
「そう思いたければ勝手にするがいい。お前の望むことは出来ないが」
「あら、いい男なのにホモなの? 残念」
透に抱き付いていた少女は、急激に興味を失った様子で、彼を解放してベッドに腰掛けた。
「まぁいいけど。あたしに落ちない男を抱いても、面白くないもの」
「お前はそれでいいのか?」
「お金には困ってないの。ただ、イケメンなお兄さんが興奮する姿を見てみたかったのよ。だって、なんか超然とした感じだったんだもん」
組んだ足を、ミニスカートがめくれあがる程に上げて透を挑発するが、彼が全く興味を示さないのを見て、逆に楽しげに微笑んでいる。
「あたし、ホモを引っ掛けたの初めてよ。お兄さんは、どんな男とならセックスするの?」
「相手が男だろうが女だろうが、俺に生殖能力はない」
「ふうん、なんか、変わってるね」
少女は、興味深そうに組んだ足の上で頬杖をつき、透を見上げた。透はといえば、目を細めて自分を見上げる少女を見下ろしていた。その闇色の瞳は、穏やかな色を湛えている。
「あのね、ママが昔から面白い話をしてくれてるんだ。あ、ママってのはあたしのお母さんね。ママも昔、男を引っ掛けてたんだけど、ある時ね、妊娠しているからこういうことはもうやめろって、言ってきた変わった男の人がいたんだって。その人も、なんか生殖能力がないとか、おかしなこと言ったって言ってたよ。お兄さん、もしかして親戚?」
「さぁな。俺は一人だ」
遠い目をして微笑みを浮かべた透は、それ以上は何も言わなかった。
「まさか、娘のあたしも同じようなおかしな男の人を引っ掛けちゃうなんてね。親子って似るのかなぁ。結局、その時の妊娠は流れちゃって、ママはホッとしたって。行きずりの男が相手だったから、産みたくなかったんだって。それで懲りて男を引っ掛けるのやめたらパパにナンパされて、付き合いだしてすぐにあたしが出来たんだって。もうね、物心ついた頃からその話を聞かされちゃってさ、耳にタコが出来ちゃってんのよね。だからって、あたしにウリやめろとは、言わないんだけど」
「ふん、止められていないのか」
「うん。どうせ言ったって聞かないでしょって。でも、ちゃんと自分で自分の体を管理してるならいいって、言ってるよ。だから、あたしは引っ掛けた男にはコンドーム渡すし、付けたの見てからやらせるしね。お金もらうんだから、そこはちゃんとしとかなきゃ」
屈託無く笑う少女は、自分なりに人生を楽しんでいるようだ。しかし、透の目には彼女の寿命が見えていた。
「お前は、自分の体のことを知っているのか」
「知ってるよ。なんで分かったの? ママとパパには言ってないんだけどさ。言ったら絶対に、家から出してもらえなくなるから」
「お前が死ねば、哀しむぞ」
「うん、分かってるけど。なんかさ、人の寿命って決められちゃってるのかなって、思うんだよね。だって、あたしまだ17歳だよ。なのに、進行性のガンなんて。分かった時には手の施しようがないなんてさ、神様って不公平だよね」
そう笑う少女の目からは、涙が零れ落ちた。両親には風邪だと話していると言った。医者にも、そう言う様に頼んだのだと。そうでも言わないと、特に母親は自分の責任だと、昔バカをやっていた自分のせいだと責めかねないと。
「神が不公平というのは、同意だな。長く生きさせたい人間ほど、早く死ぬ」
「そういう人が、いたの?」
「今、目の前にいる」
「…………」
透の静かな言葉に少女は目を見開き、そして「ありがとう」と微笑んだ。
「ねぇ、頼みごとしてもいい?」
「なんだ?」
「あたしが死んで、ママとパパが自暴自棄になっちゃったら、あたしがママとパパの子供に産まれて生きられたこと、幸せだったって伝えてほしいんだ」
「どこの誰かも、分からないのにか?」
敢えて、透がそんな話をすると、少女はバッグから一枚のカードを取り出した。
「これ、パパの名刺なの。見ず知らずの人に頼むのもおかしなことだけど、なんかお兄さんは大丈夫って気がするんだよね。あたしが誰か、本当は分かってるんじゃない?」
「…………」
透は何も答えず、その名刺も受け取らなかった。少女も何かを感じたのか、しつこく頼むことはせず、父親の名刺をバッグにしまった。
「やっぱりね。ママが言ってた変わった男の人って、お兄さんでしょ?」
「どうしてそう思うんだ?」
「何となく。あたしの主治医が言ってたんだ。この世には神様みたいな人がいるって。そして、死にそうな人のところに来て、頼み事を聞いてくれるんだって。そういう話を自分にしてくれた患者が何人かいたんだってさ。その人たちは、もうみんな死んじゃっているけど。あ、神様みたいな人って言うのは、神様って言うとその人が物凄く拒否るからなんだって」
その時の様子を思い出し、少女はクスクスと笑いながら言う。
「お前の主治医というのは志郎か」
「あ、やっぱり、知ってたんだ。そうだよ、筧志郎先生。50歳過ぎてるけど、とってもイケメンでちょっと憧れてるんだ」
「志郎なら、お前の両親にも話はいっているぞ。あいつはそういう奴だ」
「ええ? もう、先生ってば信用出来ないなぁ」
そう口を尖らせて言うが、本気で怒っていないことは、その表情から見て取れる。とても風邪とは言い難い症状を両親に見られてしまった時、何も言わなかったのは知っていたからなのだ。そうと分かり、少女は却って気が楽になった。
「じゃあ、あたしの頼み事は取り消しかな」
「その方がいいだろう」
重々しくうなずく透に向け、少女は意味深長な笑みを見せた。
「ねぇ、お兄さんやっぱり神様でしょ? なんで違うなんて言うの?」
その問いに、透はしばらく無言に徹していたが、「言ってくれなかったら、志郎先生にお兄さんに会ったって報告して、やっぱり神様だったって言っちゃうよ」と言われ、仕方なく口を開いた。
「俺が神なら、運命を変えることが可能だろう。だが俺には、予定調和の中で足掻くことしか出来ん」
「神様なら、あたしの寿命も変えられた?」
「ああ……そうだな」
少女から目を逸らし、透は窓の外に視線を向けた。その後ろ姿に、少女は言い様のない孤独と哀愁を感じた。
「寂しい?」
「そんな感情はない。全ての命は俺の元を通り過ぎていくだけだ。ただ……」
一旦言葉を切った透は一呼吸置き、再び言葉を紡いだ。
「お前たちの行く末を見届けることは、俺の責任だろうな」
「あたしたちって、人間ってこと?」
「ここに生きる全ての生命のことだ」
少しだけ透は振り返り、少女は彼の穏やかな横顔を見た。そこからは感傷的なものは見られず、滔々とした雰囲気と言葉の響きがあるだけだった。
「……それって大げさって笑ったら、怒る?」
「いいや。お前たちなら、そう感じるだろう。当然のことだ」
「でもさ、知っている人はみんな死んでいなくなっちゃうんでしょ? それって哀しくない?」
今度は体ごと振り返り、透は窓ガラスに背中を預けた。その表情は穏やかに微笑を浮かべている。
「そんな感情はないと言っただろう。そう見えるなら、お前たちがそういう感傷を抱いているからだ」
「ふうん、そういうものなの。何か、羨ましいな」
「俺がか?」
「うん。だって、寂しいとか哀しいとか、そういう感情がないって楽じゃない? あたしなんか、あたしが死んだらママやパパ、妹も哀しむだろうなって。そう思うとやりきれないよ」
ポスッとベッドに体を横たえ、少女はポツリと言った。
「あたしは、自分が死ぬことは覚悟が出来てるけど、ママたちが心配」
「そういう感情は、お前たち人間だけが持っているものだ。大切にするんだな」
「あたしは要らない。泣きたくなるだけだもん」
少女の目から零れた涙は、ベッドのシーツを濡らしている。密やかな嗚咽はベッドに吸収され、しばし静寂の時が流れた。
「感情は哀惜だけではないだろう。楽しいと思うこともないのだぞ。お前の人生は、そんなに無虚なものだったのか?」
「そうじゃないけど……でも、そっか。楽しいって大事なことだよね」
「お前は、見ず知らずの男と肌を重ねることに、生きる悦びを見出してきたのだろう」
「そんなご大層なものじゃないけど。死んじゃうって分かっていると、誰かと繋がりたいって思うものなのかな」
上体を起こした少女は泣いた顔を笑いに変え、乱れた髪を手ぐしで整えた。
「ウリを始めたのは病気が分かってからだけどね。でも、変な男の人には声を掛けないんだよ。あたしの好みの男だけ。時々、嫌なオジサンが声を掛けてくるから、その時は逃げるんだ」
「それも、もう止めておくんだな」
「どうして? ママの時みたいに?」
「病の侵食は止められず、鎮痛剤の服用も増えているだろう。その内に逃げることは容易ではなくなる」
透の淡々とした言葉に、少女は息を呑んでうなだれた。
「うん……ガンが普通の細胞を侵食する時って、本当に痛いの。体が引き裂かれるみたい。でも、最近はあまり痛くないんだ。これって薬が強くなっているのかな?」
「おそらくは」
「あたしの寿命は、あとどのくらい?」
うなだれたまま、落ちた髪の毛が少女の顔を覆い、その表情は透の位置からは見えない。
「分かるんでしょ? 言ってよ。憐れむのはやめて。そういう感情はないって言ったじゃない」
「53日」
「……すごい。そんなに正確に分かるんだ」
「命の期限が迫っていればな」
あまりにも具体的な日数に、少女は僅かに慄いた。覚悟はしていても、17歳の子供には重い数字である。しかし、少女は努めて明るく問いを重ねた。
「ねぇ、死ぬ時のあたしって、どんな感じ?」
「未来は見えん。ただ、寿命の尽きる日が分かるだけだ」
「それも何だか哀しいね。あと53日か。どうやって生きよう? あ、でも桜が見られるのは嬉しいな」
少女は顔を上げ、瞳を閉じた。桜花の吹雪く光景を想像しているのだろうか。
「後悔のないように。俺が言えるのはそれだけだ」
少女に向け、透の穏やかで優しい声音が響く。
「他に出来ることってないの?」
「お前が痛みに耐えられなくなったら、それを和らげよう。そのくらいだな」
「ガンを消してって言ったら、やってくれる?」
「神ではないと言っただろう。やれるならとっくにやっている。失いたくない人間は、他にもいた」
「助けたくても、出来ないんだ。ごめんね、嫌なこと訊いて」
命の期限が見えても、それを助けることの出来ないもどかしさは、想像しても理解の出来るものではない。少女は今日初めて出会った男を見つめ、「やっぱり哀しい人なんだね」と呟いた。